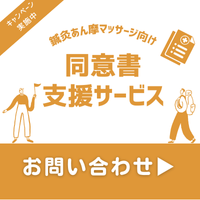鍼灸院で保険施術はできる?保険請求の仕組みと必要な準備について
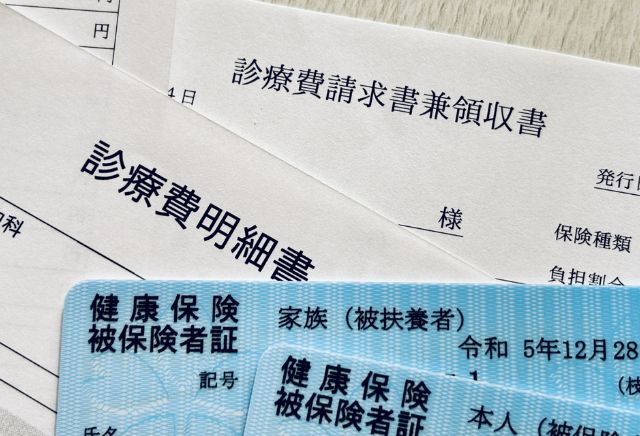
鍼灸院を開業して間もない方の中には、鍼灸院で保険施術ができるかどうかを知りたい方も多いのではないでしょうか。
結論から述べると、鍼灸院は一定の要件を満たすことで保険施術を行えるようになります。保険施術の提供によって集客力向上や売上の安定化を図りたい方は、鍼灸院が保険施術を行うために必要な要件を知っておくことが重要です。
今回は、鍼灸院で保険施術を行うための要件を紹介した上で、保険請求の仕組みと保険施術に必要な準備を解説します。
目次
1. そもそも保険施術とは?
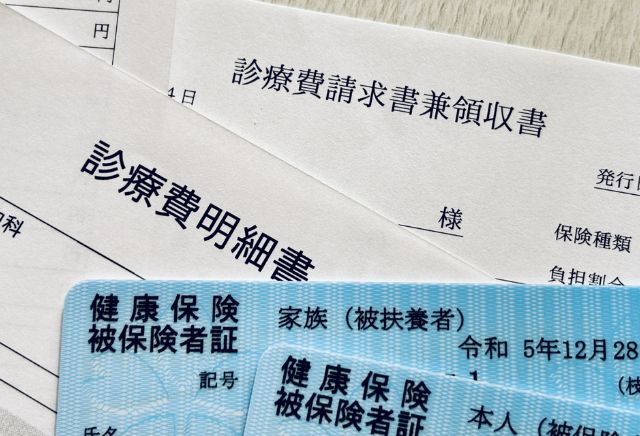
保険施術とは、施術費用の支払いに健康保険が適用される施術のことです。健康保険が適用されると窓口での自己負担額が原則3割(年齢や所得により1割・2割)に減額されて、お客様は少ない費用で施術を受けられます。
対して、健康保険が適用されない施術は「自費施術」と呼ばれます。自費施術では、お客様は健康保険による自己負担額の減額が受けられず、施術費用を全額自己負担で支払う必要があります。
1-1. 鍼灸院における保険施術の重要性
保険施術はお客様にとっては「健康保険が適用される施術」であり、鍼灸院側にとっては「保険請求ができる施術」です。
保険請求とは、支払った療養費のうち健康保険が適用される金額について、保険者に請求することを指します。
保険施術を行うと健康保険の適用により療養費が安く済むため、下記のようなメリットがあります。
● お客様の来店ハードルが下がり、集客力が高まる
● 継続的な来店を促し、売上の安定化につながる
● 競合との差別化を図れることで、競争力が強化する
反対に、保険施術を行わない鍼灸院では費用面での来店ハードルが高く、継続的な来店の促進や競合との差別化も難しいため売上を伸ばしにくいと言えるでしょう。
鍼灸院の経営を安定させるためには、保険施術を行うことが重要です。
2. 鍼灸院で保険施術を行うための2つの要件

鍼灸院で保険施術を行うことは可能です。
しかし、保険施術を提供するには2つの要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は保険施術の対象とならないため、鍼灸院の経営者は保険施術の要件を把握しておきましょう。
以下では、鍼灸院で保険施術を行うための2つの要件を解説します。
出典:全国健康保険協会「はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方」2-1. (1)保険施術の対象となる傷病であること
1つ目の要件は、改善を目的とする症状が「保険施術の対象となる傷病であること」です。鍼灸院の保険施術では、下記の症状が対象の傷病として認められています。
● 神経痛
● リウマチ
● 五十肩
● 頸腕症候群
● 腰痛症
● 頸椎捻挫後遺症
また、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められた慢性的な疼痛も、対象の傷病に含まれるケースがあります。
2-2. (2)医師が保険施術に同意していること
2つ目の要件は「医師が保険施術に同意していること」です。
1つ目の要件として説明した保険施術の対象となる傷病であっても、まずは医療機関で治療を行うことが求められます。適切に治療を行っても効果が表れないなどの理由があり、医師がはり・きゅうによる施術に同意した場合にのみ、鍼灸院で保険施術を提供することが可能です。
また、鍼灸院での保険施術をお客様が初回申請するときには、医師の同意書を提出してもらう必要があります。
3. 保険請求の仕組み|種類・算定できる療養費も

鍼灸院における保険請求は、療養費のうち健康保険が適用される金額を被保険者または鍼灸院が立て替えた後に、健康保険組合や市区町村などの保険者に請求する仕組みです。
保険請求をする際は「療養費支給申請書」を保険者に提出して、審査に通過すれば立て替えた分の金額が支払われます。
保険施術を行う鍼灸院は、以下で説明する保険請求の種類と、算定できる療養費についても知っておきましょう。
3-1. 保険請求の2つの種類
保険請求には、「償還払い」「受領委任払い」の2つの種類があります。
まず償還払いとは、お客様自身が保険請求を行う方法です。お客様が療養費の全額を鍼灸院の窓口で支払った上で、健康保険が適用される分の療養費を保険者に請求します。
償還払いは保険請求の原則とされている方法であるものの、お客様に経済的負担が発生します。複雑な保険請求をお客様自身で行わなければならない点も問題となっていました。
もう1つの受領委任払いは、保険施術を提供した鍼灸院が保険請求を行う方法です。お客様が鍼灸院の窓口で自己負担額(原則3割)のみを支払い、残りの療養費を鍼灸院が一時的に立て替えて、立て替えた分の療養費を保険者に請求します。
受領委任払いは2019年1月1日から取り扱い開始となった制度で、お客様に経済的負担や保険請求の手間が発生しません。お客様が保険施術を利用しやすくなり、鍼灸院にとってはお客様の来店につながるメリットがあります。
3-2. 保険施術で算定できる療養費
鍼灸院の保険施術で算定できる療養費には、下記の6つがあります。なお、ここで紹介する療養費の金額は、2024年におけるあはき療養費の料金改定に基づいています。
●初検料
初検料は、お客さんが鍼灸院を初めて利用したときに算定する項目です。2回目以降の利用では算定しません。はり・きゅうのいずれか一方で施術する「1術」は1,950円、はり・きゅうを併用する「2術」では2,230円で算定します。
●施術料
施術料は、はり・きゅうの施術にかかった料金を算定する項目です。1術の場合は1回につき1,610円、2術の場合は1回につき1,770円を算定します。また、2024年10月1日に訪問施術料が新設されており、訪問施術料1~3の区分で療養費の算定を行います。
●電療料
施術に電気針・電気温灸器・電気光線器具を使用した場合は、1回につき100円を施術料に加算します。
●特別地域加算
訪問看護療養費における「特別地域訪問看護加算」の地域に居住するお客様への施術1回につき、250円を施術料に加算します。2024年10月1日に新設された算定項目です。
●往療料
往療料は、突発的な往療の求めに応じた場合に算定する項目です。1回につき2,300円を算定します。なお、往療を必要とする絶対的な理由がある場合を除き、片道16kmを超える場合の往療では往療料の算定が認められません。
●施術報告書交付料
施術報告書を作成してお客様に交付した場合に、480円を算定します。
出典:厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」なお、鍼灸開業の流れについて知りたい方は、ぜひ下記のコラムも併せてご覧ください。
【最新版】あはき向け|医師に同意書を書いてもらえない場合の解決方法について解説
鍼灸院の集客方法全9選|オフラインとオンラインに分けて紹介!
4. 【5STEP】鍼灸院で保険施術を行うための準備

鍼灸院で保険施術を行うためにはいくつかの準備が必要です。
最後に、鍼灸院を開設してから保険施術を行えるようになるまでの準備を、5つのステップに分けて解説します。
【STEP1:鍼灸院の施設所開設届を提出する】
鍼灸院を開設後10日以内に、所在する地域を管轄する地方厚生(支)局に対して施設所開設届を提出します。
【STEP2:地方厚生(支)局に受領委任の申し出を行う】
地方厚生(支)局に対して受領委任の申し出を行います。受領委任の申し出には下記の書類が必要です。
| 必要な様式 |
|
|---|---|
| 添付書類 |
|
なお、提出を求められる書類は地方厚生(支)局によって異なる場合があります。受領委任の申し出を行う前に、あらかじめ確認するとよいでしょう。
【STEP3:登録記号番号を取得する】
受領委任の申し出の承認後、地方厚生(支)局から10桁の登録記号番号が交付されます。登録記号番号は、保険者に療養費を請求するときに必要となる番号です。
【STEP4:医師の同意書を取得する】
お客様に保険施術を行う前に、医師の同意書を取得します。同意書の有効期間は6か月であり、6か月を超える場合は同意書を再度取得する必要があります。
【STEP5:療養費支給申請書を作成する】
療養費支給申請書を作成して、お客様に署名してもらいます。療養費支給申請書の作成時には、保険者が変更されていないかや、お客様の被保険者資格が喪失していないかをよく確認してください。
なお、保険者が償還払いのみを受け付けている場合はお客様自身で保険請求を行う必要があるため、領収書を作成してお客様に交付します。
まとめ
鍼灸院で保険施術を行えるのは、保険施術の対象となる傷病であり、医師の同意を得ている場合のみです。保険施術を提供したい経営者の方は、保険請求の仕組みを理解した上で準備を進めましょう。
鍼灸院が安定的な経営を目指すには、保険施術だけでなく自費施術にも力を入れることが重要です。
全国統合医療協会では、手間の多い保険請求業務をサポートする「療養費請求代行サービス」や、鍼灸院の運営に関するアドバイスも行っております。保険施術・自費施術について悩みや不安がある方は、全国統合医療協会にご相談ください。
この記事の監修者

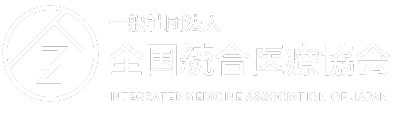




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら