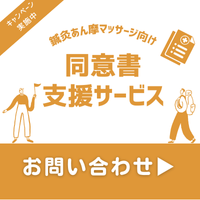【14STEP】接骨院(整骨院)の開業の流れ|成功に導くポイントも

整骨院は体の不具合の改善だけでなく、スポーツや事故などによる外傷の治療などさまざまな施術を行います。幅広い世代の患者さんから需要があり、やりがいのある仕事です。将来性があることから、開業を目指す方も多く見られます。
整骨院開業を目指すにあたって、気になることや不安はできるだけ解消しておきましょう。
今回は、整骨院を開業する場合の流れとスケジュール感、やるべきことについて詳しく解説します。整骨院開業を成功させるポイントにも触れるため、ぜひ参考にしてください。
目次
- 1. 整骨院(接骨院)開業の流れを14のステップで徹底紹介!
- 1-1. 【STEP1】施術管理者の要件を確認する
- 1-2. 【STEP2】事業計画を立てる
- 1-3. 【STEP3】資金計画を立てる
- 1-4. 【STEP4】開業エリアを決める
- 1-5. 【STEP5】開業物件を選ぶ
- 1-6. 【STEP6】コンセプトを設計する
- 1-7. 【STEP7】外装・内装の改装工事を行う
- 1-8. 【STEP8】医療機器・備品を選定する
- 1-9. 【STEP9】整骨院の開業申請手続きを行う
- 1-10. 【STEP10】療養費の請求方法を決める
- 1-11. 【STEP11】院内オペレーションを検討する
- 1-12. 【STEP12】人材採用・スタッフ教育を行う
- 1-13. 【STEP13】広告宣伝活動・各種ツール制作を行う
- 1-14. 【STEP14】プレオープンの準備をする
- 2. 整骨院開業を成功させるためのポイント
- 3. 整骨院の開業なら「全国統合医療協会」がおすすめ!
- まとめ
1. 整骨院(接骨院)開業の流れを14のステップで徹底紹介!

整骨院を開業するには、開業予定日の1年半前から準備が必要です。開業日のギリギリまでやらなければならないことがあるため、まずは全体的なスケジュールをイメージしておきましょう。
整骨院開業の流れとスケジュールは、下記の通りです。
| STEP1 | 施術管理者の要件を確認する | 開業日から1年半~1年前 |
|---|---|---|
| STEP2 | 事業計画を立てる | 開業から1年~6か月前 |
| STEP3 | 資金計画を立てる | |
| STEP4 | 開業エリアを決める | |
| STEP5 | 開業物件を選ぶ | |
| STEP6 | コンセプトを設計する | |
| STEP7 | 外装・内装の改装工事を行う | 開業から6か月~3か月前 |
| STEP8 | 医療機器・備品を選定する | |
| STEP9 | 整骨院の開業申請手続きを行う | 開業から3か月前 |
| STEP10 | 療養費の請求方法を決める | |
| STEP11 | 院内オペレーションを検討する | |
| STEP12 | 人材採用・スタッフ教育を行う | 開業から2か月前 |
| STEP13 | 広告宣伝活動・各種ツール制作を行う | |
| STEP14 | プレオープンの準備をする | プレオープンから2か月~1か月前 |
ここからは、整骨院開業までの流れをステップごとに詳しく解説します。
1-1. 【STEP1】施術管理者の要件を確認する
整骨院の開業には、柔道整復師免許の取得だけでなく施術管理者の要件を満たすことも求められます。施術管理者とは、施術で発生する療養費を受領委任で取り扱う人です。
施術管理者になるために必要な要件は、次の通りです。
● 実務経験期間の証明
● 施術管理者研修の受講
施術管理者は、一定期間の実務経験を積まなければなることができません。2024年4月以降に施術管理者の届出を出す場合は、実務経験が通算3年以上必要です。パートやアルバイトも該当するものの、介護施設・デイサービス・未登録施術所での実務経験は認められないため注意しましょう。
施術管理者研修は、保険請求に必要な知識の習得や質の高い施術スキルを身につけることを目的とした研修です。必要な研修の受講時間は16時間以上で、受講が完了すると修了証が発行されます。修了証の有効期限は、研修修了年月日から5年です。
それぞれの要件を満たしたのち、実務経験期間証明書と施術管理者研修の修了証(写し)を地方厚生(支)局へ提出します。まずは必要な実務経験を積んだ上で、施術管理者研修を受講しましょう。
1-2. 【STEP2】事業計画を立てる
事業計画とは、事業の目標を達成するために必要とされる具体的な行動を表したものを指します。整骨院開業を成功させるには、事業計画をしっかり立てることが大切です。
事業計画書は、金融機関から融資を受けるためにも必要な書類です。目指す整骨院のビジョンが明確に伝わるようにまとめましょう。
事業計画に記載する主な内容は、次の通りです。
● 事業を始める動機
● 経営者の略歴
● 施術サービスの内容
● ターゲット層
● スタッフの雇用
● 借り入れ状況
● 事業の見通し
「なぜ開業したいのか」「どのような施術を提供するのか」「スタッフは何人か」など、具体的にイメージできるかどうかがポイントです。
1-3. 【STEP3】資金計画を立てる
事業計画をもとに、工事費や医療機器の購入費、家賃、人件費など、整骨院を開業・運営するために必要な費用を算出し、資金の大まかな金額を決定しましょう。
整骨院の規模や立地、医療機器の購入方法などによって異なるものの、整骨院の開業にかかる資金は一般的に数百~1,000万円程度と言われています。大まかな金額が決まったら、資金を調達するための方法や計画について検討しましょう。
| 資金調達の主な方法 |
|---|
|
●自己資金 開業資金に自己資金を充てる方法があります。自己資金を充てるメリットは、資金の使用用途が制限されないことです。利息が発生しないため、資金繰りの負担を軽減できます。一方で、事業拡大までには時間がかかる点がデメリットです。 すべての費用を自己資金で負担することが難しくても、50万~200万円の自己資金を確保しておきましょう。自己資金がゼロの状態では、金融機関からの融資を受けられない場合があります。 ●銀行・信用金庫 自己資金を充てて不足する分は、銀行や信用金庫からの融資でカバーできます。金融機関からの資金調達は、対外的な信頼や信用につながりやすいことや開業時の負担を抑えられることが主なメリットです。 ただし、銀行は審査が厳しく手続きが煩雑なため、融資を受けるには時間がかかります。信用金庫は営業エリアが決まっており、利便性が劣る点がデメリットです。 ●日本政策金融公庫 日本政策金融公庫では、中小企業の資金調達サポートを行っています。金利が低く長期返済も可能です。審査に通りやすく経営のアドバイスも受けられるのが魅力です。 日本政策金融公庫の融資は、金融機関に比べて審査日数が長く、資金調達に時間がかかります。また、保証人が必要となることや融資金額の3割の自己資金が必要となることがデメリットに感じる方もいるでしょう。 |
なお、銀行・信用金庫・日本政策金融公庫といった金融機関から融資を受ける場合、借入先や借入希望額によっては開業のためにどれくらいの費用が必要なのか細かく聞かれます。調達した資金を内外装工事費用や院内機器・設備の購入費用に充てたいと考えている場合は、事前に諸費用をある程度把握しておかなければなりません。
融資が実行されるまでの期間は、資金調達の相談から2週間~1か月程度が基本ですが、遅ければ1か月以上かかる場合もあります。内外装工事の見積もり・購入したい設備の選定は、事前に済ませておくか資金調達の相談と併行しておくと安心です。
整骨院開業に必要な資金を確保するために、自治体の助成金制度をうまく活用するのもおすすめです。整骨院開業で利用できる補助金・助成金制度について詳しく知りたい方は、下記の記事をチェックしてみましょう。
関連記事:【2024年】整骨院の開業で利用できる補助金・助成金制度4選
1-4. 【STEP4】開業エリアを決める
事業計画の構想をもとに、整骨院を開業したいエリアを選びます。
「子育て世帯が多いエリア」「駅が近く社会人が多いエリア」「高齢者が多いエリア」など各エリアの特徴をリサーチした上で、エリアの市場調査を行いましょう。
市場調査におけるチェックポイントは、下記の通りです。
● 地域の商圏
● 競合の有無
● 交通アクセス
● 周辺の雰囲気
整骨院は競合が多い業界のため、経営を成功させるには競合との差別化が欠かせません。競合の施設数や立地、提供するサービス内容も把握しておきましょう。
人の流れや周辺の雰囲気など、実際に足を運ばなければ分からないこともあります。ターゲット層の視点を意識しつつ、物件をチェックしましょう。
1-5. 【STEP5】開業物件を選ぶ
開業エリアが決定次第、物件探しを開始します。開業物件の候補をいくつか挙げて、理想にぴったりの物件を選びましょう。
物件選びのチェックポイントは、次の通りです。
● イメージしているレイアウトにできるか
● 施術ベッドや機器を置くスペースを確保できるか
● 資金面で無理が生じない家賃設定か
● 患者さんやスタッフが利用しやすい構造か
● 水回りやトイレの位置に問題はないか
● 整骨院開業の規定を満たす面積か
● 消防設備基準を満たしているか
● 退去時の条件に問題はないか
● 看板の設置に規制はないか
整骨院の開業物件は、「テナント」「マンションの一室」「自宅の一部」の3つが考えられます。それぞれのメリット・デメリットは、以下の通りです。
●テナント
テナントは豊富な選択肢の中から理想的な物件を選べます。看板の設置に規制がないこともメリットです。ただし、物件の取得費用や固定費が高くなるといったデメリットもあります。
●マンションの一室
テナントと同様に物件の選択肢が豊富です。テナントに比べて物件の取得費用を抑えられるのがメリットです。一方で、貸主に営業許可を得る必要があり、場合によっては看板を出せないこともあります。
●自宅の一部
自宅で開業する場合、物件の取得費用がかかりません。内装や設備によっては工事をせずに開業できる可能性もあります。ただし、立地を選ぶことができない上に、プライバシーの確保が難しいといったデメリットもあります。
いずれにもメリット・デメリットがあるものの、立地面や集客面において優位性が最も高いのはテナントと言えるでしょう。
1-6. 【STEP6】コンセプトを設計する
整骨院の事業目標をもとに、自院のコンセプトを設計して施術メニューや外装・内装を検討します。
コンセプト作りのポイントは、下記の通りです。
● ターゲット層を明確にする
● 患者さんにとってのメリットを考える
● 他院との差別化を図る
自院ならではの自費メニューは、他院との差別化に効果的です。自費メニューを確立できれば、経営の安定を目指しやすくなります。ターゲット層に好まれるオリジナルメニューを考案し、黒字経営を維持できる仕組みを作りましょう。
1-7. 【STEP7】外装・内装の改装工事を行う
自院のコンセプトが定まり、外装や内装のイメージが固まったら、物件のレイアウト設計や外装・内装工事に進みます。整骨院の外装はコンセプトに応じて自由に設計できますが、レイアウトや内装は「構造設備基準」「衛生上必要な措置」を満たす必要があります。
構造設備基準と衛生上必要な措置の詳細は、下記の通りです。
| 構造設備基準 | ● 6.6平方メートル以上の専用の施術室がある ● 3.3平方メートル以上の待合室がある ● 施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できる ● 施術に用いる器具や手指等の消毒設備がある |
|---|---|
| 衛生上必要な措置 | ● 常に清潔に保たれている ● 採光、照明及び換気が充分になされている |
施術の内容や手順を考慮した上で、医療機器の設置場所・コンセントの位置や動線についてよく考えることも大切です。工事業者やすでに開業している先輩、医療機器業者などに相談し、スムーズに施術できる空間を作りましょう。
1-8. 【STEP8】医療機器・備品を選定する
整骨院の外装・内装工事を進めるとともに、院内で使用する医療機器や備品の選定を行いましょう。医療機器は、実際に体験した上で導入を検討するのがポイントです。
医療機器はメーカーやディーラーから直接購入する方法もありますが、保険付帯のリースを活用する方も少なくありません。開業資金を節約したい方はリースを検討してみるとよいでしょう。リースの場合でも、リース料金を全額経費計上できます。
整骨院で使用する備品としては、ベッドやタオル類、カルテを収納するキャビネット、待合室のソファやイスなどが挙げられます。購入決定から搬入まで時間がかかる場合もあるため、余裕をもって搬入できるようスケジュール調整を行いましょう。
「全国統合医療協会」では、アウターマッスルとインナーマッスルの両方を効果的に鍛えられる複合高周波EMS「ELbio」のほか、施術に使用できる多様な機器を提供しています。自費メニューを導入したい方・競合との差別化を図りたい方は、ぜひ下記ページからお問い合わせください。
1-9. 【STEP9】整骨院の開業申請手続きを行う
物件の改装工事や医療機器・備品の手配と併せて、整骨院の開業申請手続きを行いましょう。整骨院を開業するためには、主に以下の届出を行う必要があります。
【整骨院の開業に必要な申請手続きと届出先】
| 申請手続き | 必要書類 | 届出先 |
|---|---|---|
| 施設所開設届 |
|
管轄の保健所 |
| 領委任の取り扱いに関わる申し出 ※保険請求を行うために必要 |
|
管轄の地方厚生局 |
| 共済番号の取得 ※国家公務員や地方公務員、防衛省関係の保険を取り扱うために必要 |
|
共済組合・防衛省 |
| 税務署への届出 |
|
管轄の税務署 |
| 労災保険指定医療機関への届出 ※労災保険を取り扱うために必要 |
|
管轄の都道府県労働局 |
施術所開設届は、必要書類を添付して開設後10日以内に管轄の保健所へ届出します。個人事業主としての開業届は、事業開始から1か月以内に税務署へ提出が必要です。
申請手続きによって必要書類や届出先が異なるため、スケジュールに余裕をもって準備しておきましょう。
1-10. 【STEP10】療養費の請求方法を決める
保険請求を行うためには、療養費の請求方法を決めておく必要があります。療養費の請求方法には、個人請求と請求代行の2種類があります。院によってベストな請求方法は異なるため、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解した上で、適した方法を選択しましょう。
個人請求は、請求ソフトなどを利用して施術者が直接請求業務を行います。請求代行は、請求業務を請求団体に委託する方法です。
個人請求と請求代行には、それぞれ以下のメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 個人請求 |
|
|
| 請求代行 |
|
|
初期コストをできるだけ抑えたい方や療養費のノウハウを身につけたい方には、個人請求がおすすめです。本業に専念したい方や請求業務以外のサポートも受けたい方は、請求代行の利用を検討してみましょう。
請求団体を利用する場合は、「業務の流れが明確か」「入金管理がしっかりしているか」に注目して団体を選ぶのがポイントです。セキュリティ対策やフォロー体制も比較して、信頼できる団体に委託しましょう。
1-11. 【STEP11】院内オペレーションを検討する
円滑な運営を目指すために、院内オペレーションを検討します。院内オペレーションとは、整骨院を運営するためのビジネスシステムやマネジメントを意味します。
業務の品質を保つには、接客や施術のマニュアル化、在庫管理システムの導入など、日々の業務を効率化したり可視化したりすることがポイントです。
開業後に課題や問題が発生することもあるため、まずは大まかな院内オペレーションを設計して、必要に応じて見直しと改善を行いましょう。
1-12. 【STEP12】人材採用・スタッフ教育を行う
整骨院の開業にあたり、新たにスタッフを確保する必要がある場合は、早めに求人サイトなどを活用してスタッフの募集を行いましょう。即戦力となるスタッフを求める場合は、中途採用が適しています。自費メニューを提供する場合は、ヘルスケア関連の職種を採用も検討してみましょう。
スタッフの教育には、院内で使用する人材育成マニュアルの作成や研修・講習の実施が効果的です。開業当日からスムーズに勤務してもらえるよう、開業前に余裕をもってスタッフを採用し、教育を行っておきましょう。
1-13. 【STEP13】広告宣伝活動・各種ツール制作を行う
来院する患者さんを増やすためには、地域の方に自身の整骨院を知ってもらう必要があります。オフライン施策とオンライン施策をうまく活用して、広告宣伝活動を積極的に行いましょう。
広告宣伝活動に効果的な施策例は、下記の通りです。
| オフライン施策 |
|
|---|---|
| オンライン施策 |
|
開業前後だけでなく、開業後も定期的に情報を更新し、新しい施術メニューや整骨院に関するお得な情報などを提供することも大切です。
整骨院の認知度や患者の満足度を高めるには、問診票・診察券・院内POPなどのツール制作も欠かせません。自院の魅力が伝わるように、テーマカラーやコンセプトイメージに合わせて作成しましょう。
各種ツール制作には手間と時間がかかるため、専門の業者に依頼するのも1つの方法です。
関連記事:整骨院・接骨院の集客方法9選|ホームページ集客の成功ポイントも
また、整骨院の広告に記載できる事項は柔道整復師法によって定められています。広告規則に違反する内容を記載した場合、罰則の対象となるため注意が必要です。
整骨院の広告に記載できる事項例と記載できない事項例は、次の通りです。
| 記載できる事項 | 記載できない事項 |
|---|---|
|
|
医療保険療養費支給申請ができることを記載する場合は、「脱臼または骨折部分の施術に係る申請については医師の同意が必要である」と明示しなければなりません。
整骨院の広告制限についてより詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:整骨院の広告制限・広告ガイドラインとは?NG・OKな表現も紹介!
1-14. 【STEP14】プレオープンの準備をする
プレオープンを行う場合は、予定日に間に合うように準備を進めておきましょう。
開業プレオープンとは、本格的に整骨院をオープンする前に試験的に営業することです。開業日の数日前に実施するケースが一般的です。試験的に営業することで、オペレーションがうまく機能するかどうかを確認できます。
プレオープンを行うにあたり、日数の決定や招待客の選定などやらなければならないことは数多くあります。準備を滞りなく進めるために、詳細なスケジュールを設定しましょう。招待客への告知は、予定日の1か月前を目安に行うとスムーズです。
アンケート用紙やメールの準備をしておくと、整骨院を利用した招待客の意見を集めやすくなります。
2. 整骨院開業を成功させるためのポイント

整骨院開業が成功させられるかどうかは、開業準備・開業スタート時にかかっています。
開業を成功させるために、次のポイントを意識して準備を進めましょう。
2-1. コンセプト・ポジショニングを明確にする
「24時間営業の整骨院」「スポーツに特化した整骨院」など、コンセプトを具体的に作り上げてポジショニングを明確することが重要です。
利用者のニーズと院のコンセプトをマッチさせることができれば、安定した集客を維持しやすくなります。コンセプト作りでは、雑誌やSNSなどの情報が参考になる場合があります。競合の動向もチェックしつつ、利用者が来院したくなるようなコンセプトを考えましょう。
2-2. 頼れる相談先を見つけておく
開業準備の手順を相談できたり注意点などをアドバイスしてくれたりする存在がいると、安心して準備を進めることができます。
整骨院開業時に頼れる主な団体・事業者は、下記の通りです。
●商工会議所
商工会議所には、開業を検討している方が利用できる無料相談窓口があります。事業計画書の作成や開業準備の進め方などで分からないことがあれば、気軽に相談できます。弁護士や税理士などの専門家に相談することも可能です。開業や起業に役立つセミナーやイベントも開催しているため、情報収集や地域での人脈構築にも役立ちます。
●整骨院開業コンサル・支援事業者
整骨院開業コンサルや支援事業者は、院の開業や分院展開のサポートを行います。集客ノウハウの指導や人材採用・育成のアドバイスなどをしてくれる頼もしい存在です。他院との差別化や資金調達のサポートにも対応しているため、開業時はもちろん開業後の不安も解消できます。
3. 整骨院の開業なら「全国統合医療協会」がおすすめ!

「全国統合医療協会」では、整骨院開業を目指す方のサポートを実施しています。
全国統合医療協会が行っている主なサポート内容は、下記の通りです。
● 開業支援
● 請求代行
● 融資
● WEB広告・ホームページ作成
● 店舗設営サポート
● レセコン紹介
● 医療機器紹介
開業支援はもちろん、開業後の運営業務のサポートにも対応しています。セミナーや勉強会の開催、業界の最新情報の共有にも力を入れています。
開業に不安や疑問がある方、請求業務の委託を検討している方は、全国統合医療協会をチェックしてみましょう。
まとめ
整骨院開業には、事業計画・資金計画の立案から開業エリアの選定などやらなければならないことが数多くあります。開業に向けた準備は、開業予定日の1年半前を目安に始めましょう。
開業準備をすべて1人でこなそうとすると、計画通りに進まなかったり不安になったりすることもあるため、相談できる頼れるパートナーが必要です。
開業準備のパートナーを探している方には、「全国統合医療協会」の開業・運営支援の活用がおすすめです。事業計画の作成から広告宣伝活動までの全面的なサポートを提供しているので、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

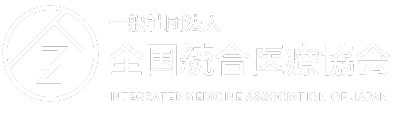




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら