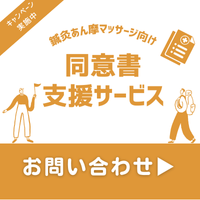整骨院の広告制限・広告ガイドラインとは?NG・OKな表現も紹介!

整骨院(接骨院)を経営する方の中には、集客のために広告を出そうと考えている方も多いでしょう。広告は多くの方に自院を知ってもらう機会をつくれますが、整骨院には「広告制限」があり、今後は「広告ガイドライン」も発出される予定である点に注意が必要です。
この記事では、整骨院における広告制限の対象や、法律による制限が設けられている背景・理由について解説します。整骨院が注意すべき広告規制のポイントや違反した場合のペナルティについても併せて確認し、適正な広告を作成するための準備を整えましょう。
目次
1. 整骨院(接骨院)の「広告制限」とは?

整骨院(接骨院)の「広告制限」とは、柔道整復師法第24条によって定められている、広告表示に関する規制です。法律で定められている事項以外の内容を広告に記載することはできないことを、必ず押さえておきましょう。
(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
(引用:e-Gov法令検索「柔道整復師法」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC1000000019_20220617_504AC0000000068)
なお、柔道整復師法第24条の「四 その他厚生労働大臣が指定する事項」の例として、大阪市が公表している下記のような内容が挙げられます。大阪市に限らず、全国の整骨院に適用される内容であることに注意しましょう。
● ほねつぎ(又は接骨)
● 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
● 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
● 予約に基づく施術の実施
● 休日又は夜間における施術の実施
● 出張による施術の実施
● 駐車設備に関する事項
(引用:大阪市「施術所の広告及び名称に関する規制」/https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000056997.html)
1-1. 整骨院における広告制限の対象
整骨院における広告は厳密に定義されており、下記のような性質をもつものはすべて広告に該当します。下記のような広告を出す場合は、法律に則って適切な内容を記載するようにしましょう。
【整骨院における「広告」の定義】
●【誘引性】…患者さん(利用者さん)を誘引する目的で作成されるもの
●【特定性】…整骨院の名称および、柔道整復業やあんま業などの施術を提供する人物の氏名が特定できるもの
●【認知性】…一般の方が認識できる状態にあるもの
つまり、不特定多数の方の目に触れやすい媒体はすべて広告制限の対象です。具体的には、下記のような媒体が制限の対象となります。
【広告制限の対象となる媒体の具体例】
● チラシ
ポスティングや新聞折込で配布するチラシや、新聞・雑誌などに掲載する広告などが該当します。
● 看板などの外観
整骨院の看板も広告制限の対象となります。外から見えるように窓やドアに貼ったポスターなどの掲示物も、制限の対象となることに留意しましょう。
● インターネット上の広告
インターネット上のバナー広告や、検索結果で上位に表示される有料オプションも広告制限を受けます。
自院のホームページやポスターなどの院内掲示物、パンフレットなどの院内配布物は、今のところ広告制限の対象外となっています。しかし、これらの媒体を見た方の誤解を招く表現や、誇大広告と考えられる表現は避けたほうが無難です。適正な表現を心がけましょう。
1-2. 広告制限の背景・理由
整骨院の広告が法律による制限を受けるようになった背景には、不適切な広告による患者さんの悪質な誘引・集客があったことが挙げられます。
患者さんの誤解を招く広告や誇大表現と考えられる広告が数多く報告されたことを受け、悪質な誘引・集客から患者さんを保護するために広告制限が設けられることになりました。
法律による広告制限は、患者さんの身体の被害や経済的損失を防ぐために必要なことです。患者さんのためにも、法律を順守し、適正かつ明確な表現の広告を作成するようにしましょう。
2. 整骨院の「広告ガイドライン」とは?
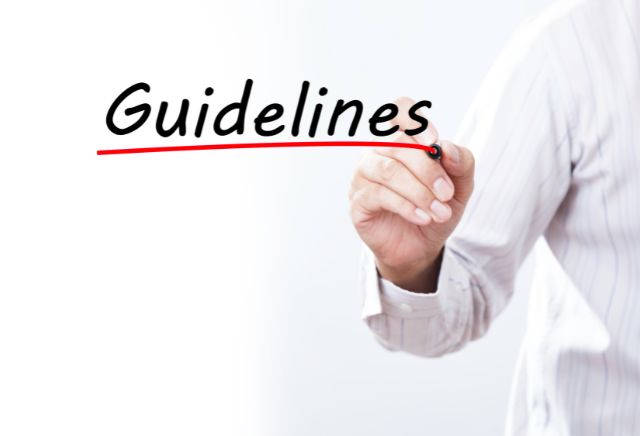
整骨院の広告ガイドラインとは、広告表示に関する規制について、整骨院の経営者向けにまとめた資料のことです。
厚生労働省は2018年、「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」を立ち上げ、柔整・あはきの施術所における広告ガイドラインを整備することになりました。整骨院の広告ガイドラインを整備する理由は、整骨院の適切な広告運用を推進し、患者さんが自分にとって利益となる施術所を選択できるようにするためです。
整骨院の広告ガイドラインは、2024年開催の第11回検討会で最終合意された案に基づき、これから調整に入って発出される予定です。6年間にわたって続いた検討会も決着を迎えつつあります。
広告ガイドラインの発出によって、患者さんは整骨院選びの判断材料を得やすくなるでしょう。
一方、患者さんが広告規制に関する知識をもつことで、広告の信頼性や適法性がより厳しく問われるようになると考えられます。整骨院の経営者にとっては、広告内容の精査が今まで以上に重要となるでしょう。
3. 【整骨院】注意すべき広告規制7つ

整骨院が広告を出す際には、法律で定められた広告制限から逸脱しないよう注意する必要があります。下記のような表現に注意した上で、広告の作成を進める必要があるでしょう。
【注意すべき7つの広告規制】
(1)景品表示法に抵触する表現
(2)薬機法・医師法に抵触する表現
(3)施術のビフォーアフター写真
(4)具体的な施術内容
(5)保険施術・自費施術の料金
(6)施術者の経歴・実績
(7)紛らわしい施術所の名称
ここでは、上記7つの規制内容について詳しく解説します。
3-1. (1)景品表示法に抵触する表現
整骨院の広告やホームページ、院内掲示物および院内配布物は、すべて景品表示法の適用対象となります。下記のような表現は景品表示法に抵触する可能性が高いため、広告などには使用しないようにしましょう。
●誇大広告
誇大広告とは、施術の効果・効能や整骨院の得意分野などを大げさに表現し、患者さんの誤解を招きかねない広告のことです。誇大広告は、実際に提供するサービスよりも良い印象を与えて不当に誘引する効果があり、患者さんの不利益につながります。
【誇大広告の例】
●「◯◯に効く」
●「健康になります」
●「✕✕の改善率◯%」
●品位を損ねる表現
品位を損ねる表現とは、広告内で料金の安さを強調するといった表現のことです。整骨院は接骨やほねつぎを役務として提供する施設であり、料金の安さを強調することは整骨院業界全体の品位を損ねるおそれがあります。
また、施術を受けることで景品をプレゼントするといった内容も、品位を損ねる表現に該当するため注意してください。
【品位を損ねる表現の例】
●「今なら◯円で△△療法を受けられます」
●「リニューアルにつきキャンペーン実施中!」
●「無料相談で◯◯を差し上げます」
●比較優良広告(優良誤認広告・有利誤認表示)
比較優良広告とは、他の整骨院と比較して、提供する施術サービスや料金などで自らの整骨院のほうが優れていると表現する広告のことです。他の整骨院との比較によって良い印象を暗示する表現であり、患者さんに誤解を与えるおそれがあります。
比較優良広告には、施術の質などを実際よりも優良に見せかける「優良誤認広告」と、施術料金などを実際よりも患者さんに有利と誤認させる「有利誤認広告」があります。
【比較優良広告の例】
●「◯◯エリアの顧客満足度NO.1!」
●「✕✕の施術で日本有数の実績を有しています」
●「△△整骨院より◯◯円も安い」
3-2. (2)薬機法・医師法に抵触する表現
整骨院での施術はもちろん、販売する健康食品やサプリメントについて医学的な効果・効能を謳って広告した場合、薬機法や医師法に抵触する可能性があるため注意が必要です。
薬機法とは、医薬品や医療機器などの品質・安全性・有効性を確保することを目的とした法律です。施術や健康食品・サプリメントなどで患者さんに医薬品と誤認させるような表現を使用すると、薬機法違反になる可能性があります。
薬機法に抵触しないためには、下記のような表現の使用を控えましょう。
【薬機法で制限される表現の例】
●「施術を受けると症状が改善する」
●「◯◯が治る・完治する」
●「サプリメントで脂肪燃焼(痩せる)」
もう1つの医師法とは、医師の資格や医師が行う医業について定めた法律です。
柔道整復術や鍼灸、あんま・マッサージ・指圧は「医療類似行為」として法律で認められているものの、医師が行う医業である「医行為」ではありません。「医師」「医行為」を想起させる言葉・表現は医師法に抵触する恐れがあるため、整骨院の広告には使用しないようにしましょう。
【医師法で制限される表現の例】
●「医師・ドクター」
●「診療・診察・問診」
●「治療」
●「初診料」
● 医療機関の受診が必要となる症状・疾病の名称
3-3. (3)施術のビフォーアフター写真
施術のビフォーアフター写真は、患者さんが「自分も治るに違いない」と誤認する可能性があります。施術の効果は患者さんによって違いがあるため、施術のビフォーアフター写真の掲載は広告規制の対象です。
同様に、施術の体験談(口コミ)も患者さんの誤解・誤認を招く可能性があるため避けたほうがよいでしょう。
なお、施術に関すること以外のコメントや、実際に通院している患者さんの写真を掲載すること自体は禁止されていませんが、患者さん本人の了承が必要となります。
3-4. (4)具体的な施術内容
自院で行う施術内容を広告でアピールしたい方も多いでしょう。「柔道整復師法」や「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)」では、取り扱っている施術の名称を下記のように記載することは可能です。
【柔道整復師法・あはき法で認められている記載(例)】
● 柔道整復師師の場合
「ほねつぎ」「接骨」
● あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の場合
「もみ療治」「やいと」「えつ」「小児鍼」
ただし、具体的な施術内容を広告に記載することは法律で禁止されていることに注意が必要です。施術の作法や流派、施術を受けることで期待される効果・効能に関する記載も禁止されていることを押さえておきましょう。
3-5. (5)保険施術・自費施術の料金
整骨院の施術料金が気になる患者さんも多いため、広告に施術料金を記載したいと考えている方も少なくないでしょう。
しかし、保険施術・自費施術ともに、広告に料金を記載することはできません。法律で決められている項目以外の内容は記載できないことに留意しましょう。
3-6. (6)施術者の経歴・実績
柔道整復師法やあはき師法では、施術者の氏名・住所を広告することは認めているものの、施術者の経歴・実績については広告を認めていません。
広告に施術者の経歴・実績などを掲載すると柔道整復師法に違反するため、下記のような内容は掲載を避けましょう。
【規制される経歴・実績掲載の例】
● 略歴や経験した施術数
● 院長、副院長といった肩書
● あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師以外の保有資格
なお、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の資格については広告への記載が認められています。「柔道整復師(国家資格保有)」のように、国家資格を保有していることの表記も可能です。
3-7. (7)紛らわしい施術所の名称
整骨院における広告ガイドラインの中でも、特に厳しく規制されているのが施術所の名称です。具体的には、下記のような名称について広告不可とされています。
●「医療」と誤解するおそれがあるものを含む名称
◯◯診療所・◯◯治療院・◯◯クリニックなど、医療を提供する場所と患者さんが誤解するおそれがある名称は使用できません。
● 何を行っているかが不明瞭な名称
◯◯堂・◯◯センター・◯◯ステーションなどは、名称だけでは何を行っている施設かが不明瞭です。患者さんが適切な施術所を選択できるよう、業態を認知できる名称を使う必要があります。
● 柔整・あはき以外の施術所とみなされる可能性のある名称
カイロプラクティック・整体院や、サロン・ほぐし処・研究所なども患者さんが業態を正しく認知できない可能性があり、広告不可とされています。
● 対象者を限定する名称
レディース専門整骨院・交通事故専門整骨院といった、対象者を限定する名称は広告に使用できません。
● 施術の技能・内容・方法を含む名称
施術の技能・内容・方法とは、東洋医学・温鍼・漢方・電気療法などのことです。これらを含む名称は広告不可とされています。
(出典:厚生労働省「「整骨院」に係るガイドライン上の取扱いについて」/https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001274652.pdf)
なお、広く使われている「整骨院」という名称について使用不可とするかどうかも、あはき師・柔整師等の広告に関する検討会では議論されています。
検討会の途中までは「開設届出済みの場合は移転・看板掛け替えなどをしない限り当面許可、新規や移転などをした場合は使用不可」という方向性で考えられていました。新規や移転の場合は、「接骨院」または「ほねつぎ」という名称を用いることとなります。
しかし、第11回検討会では「整骨院」の名称可否についてすぐに結論を出すことが難しく、今後も検討が必要な課題であるという認識で終了しています。
結果として、広告ガイドラインの中では「整骨院」の使用不可について記載しないことになりました。当面の間は開設届出済みや新規の区別なく、「整骨院」の名称を使用できる流れとなっています。
4. 整骨院の広告に掲載できる内容

これまで紹介した内容とは反対に、整骨院の広告に掲載できる内容としては下記のものが挙げられます。
● 柔道整復師である旨や、施術者の氏名・住所
● 施術所の名称と電話番号、所在地
● 施術日または施術時間
● ほねつぎまたは接骨を提供する旨
● 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術にかかわる申請は、医師の同意が必要な旨を明示する)
● 予約や出張による施術の実施
● 休日または夜間における施術の実施
● 駐車設備についての案内
なお、広告に掲載できる内容であっても、広告規制の考え方に抵触する場合は使用不可となるケースがあります。
たとえば電話番号に「1376(痛み治る)」のような語呂合わせを併記したり、医療保険療養費支給申請ができる旨で「各種保険取り扱い」と表示したりなどはできません。
5. 広告ガイドラインに違反してしまうとどうなる?

整骨院が広告制限を逸脱した広告を配布・掲示した場合、患者さんや周辺住人・通行人、同業者などが管轄する保健所や地方厚生局に通報する場合があります。通報を受けた保健所・地方厚生局が指導に入り、訪問によるチェックや注意勧告が行われたり、文書の提出が求められたりすることを押さえておきましょう。
なお、「再三の注意にかかわらず改善の兆しがない」「違法性が高い」など、悪質とみなされる場合には起訴される可能性があります。有罪が確定すると、柔道整復師法やあはき法に基づいて30万円以下の罰金が課せられることに注意してください。
まとめ
整骨院には、患者さんが不利益を被らないよう広告制限が設けられており、法律で定められた広告制限を逸脱した場合は30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。特に、チラシや看板、インターネット上の広告などを出す際には、規制されている内容を記載していないかどうか十分に確認するようにしましょう。
広告制限を逸脱しないような広告をしっかり打つためには、専門的な知識をもつ第三者に相談することも1つの方法です。広告を検討している方は、整骨院の開業支援や経営支援を広く行っている「全国統合医療協会」にぜひご相談ください。
この記事の監修者

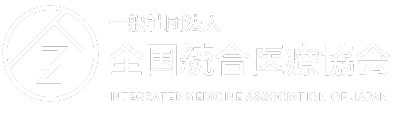




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら