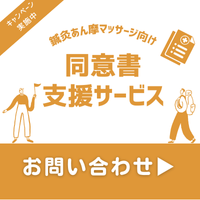整骨院の開業に必要な資格は?柔道整復師・施術管理者の取得要件

整骨院の開業を目指すにあたって、「必要な資格には何があるのか」と気になる方も多くいるでしょう。保険施術にも対応できる整骨院は、整体院やリラクゼーションサロンとは違って国が定めた一定の資格と条件を満たす必要があります。
そこで今回は、整骨院の開業にあたって必要となる資格や、資格取得までの流れについて詳しく解説します。整骨院の開業を少しでも検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 整骨院での仕事に「資格」は必要?

これから整骨院で働きたい、あるいは自身で開業したいと考えている方にとって、必要資格の有無は非常に気になるポイントでしょう。
結論から述べると、「整骨院で働く(雇用される)」だけであれば無資格でも可能です。しかし、自身で整骨院を開業したい場合は免許や資格が必要となります。
また、働く立場であっても、資格の有無によって業務内容には明確な違いがあり、施術の幅や対応範囲も大きく異なります。資格を保有していなければできない行為が法律で定められているため、資格取得の有無は整骨院でのキャリアプランを立てるうえでも大きな意味をもつと言えるでしょう。
ここからは、整骨院における資格の必要性について、「働く側」と「開業する側」それぞれの視点から詳しく紹介します。
1-1. 無資格でも働けるが「柔道整復師」としての応募はできない
整骨院では、柔道整復師以外にも受付スタッフや整体師といった職種が存在しており、これらのポジションであれば無資格者でも応募可能です。
ただし、柔道整復師として施術業務に従事するには、柔道整復師国家資格の取得が必須となります。
柔道整復師は、打撲・捻挫・骨折などの外傷に対し、手技によって整復・固定・後療法を行う「医療類似行為」が認められています。無資格者がこうした施術を行うことは、法律で禁止されています。
そのため、無資格者が整骨院で働く場合は、次のような職種に就くのが一般的です。
●受付スタッフ
来院してきたお客さんの対応や電話応対、窓口・会計業務など、主に接客と事務作業を担当します。
●整体師
主に、体のバランスを整えるリラクゼーション施術を担当します。国家資格をもたないため、健康保険が適用される保険施術や医療類似行為は行えません。
いずれも整骨院においては大切な役割ではありますが、柔道整復師と同じ施術はできないため、業務範囲には一定の制限があることを覚えておきましょう。
1-2. 開業の際は最低でも「柔道整復師免許」が必須となる
整骨院を開業するには、柔道整復師の国家資格が絶対条件です。無資格者が開業することは法律で禁じられており、仮に無資格で「整骨院」と名乗った場合は違法とみなされます。
ただし、柔道整復師の資格を有しているだけでは、保険診療を扱うことはできません。整骨院で保険施術を取り扱うためには、「施術管理者」としての届け出が必要です。これは、一定の実務経験を積んだ柔道整復師が所定の研修を修了したうえで、健康保険の受領委任を行えるよう届け出る制度です。
つまり、整骨院の開業には「柔道整復師免許」が最低限必要であり、保険施術を提供するためにはさらに「施術管理者」としての条件をクリアしなければならないことになります。
自費施術のみでの運営も可能ではありますが、保険診療がない場合は集客や経営面での工夫がより一層求められるため、初めての開業には不向きな運営スタイルとなる点に注意が必要です。
2. 整骨院の開業に必要な「柔道整復師」の概要と取得方法

前述の通り、整骨院を開業するためには「柔道整復師」の国家資格が必要です。柔道整復師は、骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの外傷に対し、手技による施術を行う専門職です。
柔道整復師資格の取得には、一定の期間と専門的な知識が求められます。資格の取得方法や国家試験の内容・難易度をしっかり理解しておくことは、スムーズな開業準備につながるでしょう。
そこで次に、柔道整復師資格取得までの流れと、柔道整復師国家試験の内容・難易度について紹介します。
2-1. 柔道整復師資格取得までの流れ
柔道整復師の資格を取得するためには、まず高校を卒業後、柔道整復師養成課程のある専門養成施設に入学し、所定のカリキュラムを修了して国家試験の受験資格を取得する必要があります。
【高校卒業から柔道整復師資格取得までのステップ】
| STEP(1) | 高校を卒業する |
|---|---|
| STEP(2) | 柔整系専門学校に入学、または柔道整復学科のある4年制大学or3年短大に入学し、所定のカリキュラムを修了する |
| STEP(3) | 国家試験を受験する |
| STEP(4) | 国家試験に合格すれば、柔道整復師資格を取得できる |
この「柔道整復師養成課程のある専門養成施設」は、主に厚生労働大臣が認可した専門学校や大学などが該当し、通常3年間の教育課程が設けられています。
主に学科では解剖学や生理学、整形外科学など医療知識の基礎を学び、実技では施術法や応急処置を習得します。卒業後は、国家試験の受験資格が与えられ、国家試験に合格すれば晴れて柔道整復師資格を取得できます。
2-2. 柔道整復師国家試験の内容と難易度
柔道整復師国家試験は毎年1回、通常2月の第3日曜日に実施されます。試験の中心は筆記試験であり、医療に関する幅広い知識が問われます。具体的には解剖学、生理学、運動学、整形外科学、衛生学、柔道整復理論など、多岐にわたる分野から出題されます。
柔道整復師国家試験の合格率はおおよそ50~65%前後で推移していることから、決して難易度の低い試験とは言えません。確実な合格を目指すには、専門的な学習と十分な準備が不可欠です。
【柔道整復師国家試験の合格率(2020年~2024年)】
| 第29回 (2020年度) |
第30回 (2021年度) |
第31回 (2022年度) |
第32回 (2023年度) |
第33回 (2024年度) |
|---|---|---|---|---|
| 66.0% | 62.9% | 49.6% | 66.4% | 57.8% |
出典:公益財団法人 柔道整復研修試験財団「1.柔道整復師国家試験の実施」
柔道整復師国家試験に合格すると柔道整復師免許が交付され、法律上、整骨院を開業したり保険適用の施術を行ったりすることが可能になります。整骨院開業を目指す方にとって、この資格取得は最も重要な第一歩と言えるでしょう。
3. 整骨院の開業に必要な「施術管理者」の概要と要件

整骨院を開業して健康保険の保険施術を提供するためには、柔道整復師資格に加えて「施術管理者」としての要件を満たさなければなりません。
そもそも施術管理者とは、保険診療の適正な実施を管理する役割をもつ専門職であり、保険施術を提供する整骨院の運営においては極めて重要なポジションとなります。
ここからは、施術管理者になるための2つの要件と、受領委任の取り扱いに関する届出方法を紹介します。
3-1. 要件(1)一定の実務経験期間
施術管理者となるためには、柔道整復師の免許取得後、整骨院や接骨院などで「3年以上」の施術経験が必要です。この経験期間は、保険施術を適切に行うための知識や技術を十分に習得し、現場での実践能力を磨くことを目的としています。
なお、必要な実務経験期間は、制度改正により段階的に引き上げられている点に注意が必要です。2018年4月~2022年3月までは1年間の経験が要件となっていましたが、2022年4月~2024年3月は2年間に変更され、2024年4月以降は3年間へとさらに延長されています。
このように、実務経験期間に関する要件は年々厳格化されているため、今後さらに長期化する可能性も考慮しておきましょう。
また、実務経験があることを証明するためには、所定の「実務経験期間証明書(別紙様式1)」の提出が不可欠です。この証明書は、柔道整復師が実務に従事していた登録施術所の管理者(開設者または施術管理者)によって発行されたものでなければなりません。
加えて、地方厚生(支)局に登録されている施術所での勤務情報は、実務経験の正当性を確認するための公式な資料として活用されます。つまり、施術所が正式に届け出されており、そこに勤務していたという記録が行政側で確認できることが前提になります。
3-2. 要件(2)施術管理者研修の修了
施術管理者になるためには、一定の実務経験期間を経ることに加え、所定の「施術管理者研修」を受講し、修了証を取得することも必須です。
施術管理者研修研修とは、柔道整復研修試験財団が主催する研修で、保険請求の仕組みや法令遵守、施術管理者としての責任と役割、適切な診療報酬請求の方法などを学びます。研修は2日間(合計16時間)実施され、受講後2週間程度で「施術管理者研修修了証」が発行されます。
施術管理者研修修了証は研修を受けた証明となり、研修修了年月日から5年間が有効期間となります。
3-3. 受領委任の取り扱いに関する届出方法
柔道整復師免許と施術管理者研修の修了証を取得して施術管理者としての要件を満たしたら、次に保険施術の保険者(健康保険組合や国民健康保険など)に対して「受領委任に関する届け出」を行います。
そもそも受領委任とは、お客さんに代わって整骨院が健康保険から施術費用を直接受け取る仕組みであり、この届け出を済ませて初めて保険施術の取り扱いが正式に認められます。届け出は各保険者ごとに提出が必要で、必要書類や手続きの詳細は保険者の指示に従って進めます。主な必要書類としては、下記が挙げられます。
● 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(施術所の申し出)
● 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)
● 確約書(様式第1号)
● 誓約書(様式2号の3)
● 欠格事由非該当届出書
● 実務経験期間証明書
● 施術管理者選任証明(※整骨院の開設者と施術管理者が異なる場合のみ)
整骨院の開業準備は、これら必要書類の提出を含む一連の手続きが完了し受理された後に、初めて進めることが可能となります。施術管理者の要件を満たすことは、開業後の経営の安定や保険施術の円滑な提供に欠かせないため、計画的に準備を進めることが重要です。
まとめ
整骨院を開業・運営するには、柔道整復師の免許を持つだけでなく、施術管理者としての資格要件を満たす必要があります。具体的には、一定期間の実務経験と施術管理者研修の修了が求められ、保険施術を行うためには受領委任の届け出も欠かせません。これらの資格取得や手続きを段階的に進めることは、円滑な整骨院経営の第一歩となります。
全国統合医療協会では、整骨院の開業に必要な資格取得から届出手続き、開業後の運営サポートまで、専門的な知見をもとに幅広く支援しています。「何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

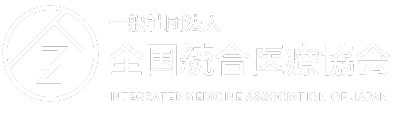




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら