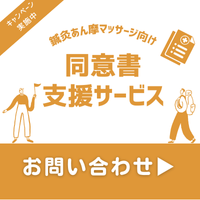接骨院で保険請求をするには?請求までの流れと必要書類について解説
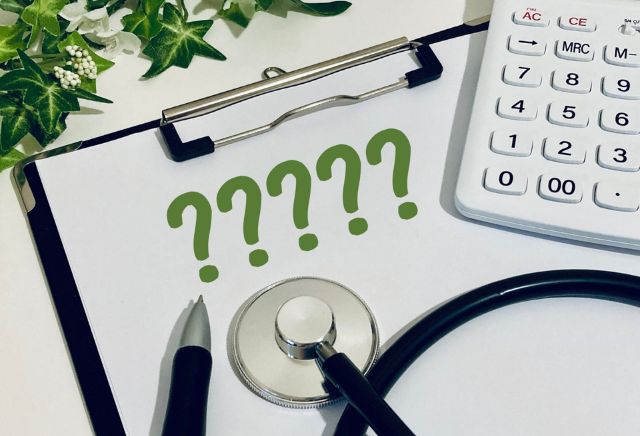
接骨院(整骨院)で保険対象の施術を提供したときは、保険者に対して保険請求を行います。整骨院の開業を考えていて「保険請求をどのように行えば良いか」「整骨院が保険請求を行うときに必要な準備は何か」と疑問や不安を感じる柔道整復師の方も多いでしょう。
接骨院が保険請求を行うには「受領委任契約」が必要です。
本記事では、整骨院が受領委任契約を交わすための必要書類や保険請求を開始できる時期、保険請求の具体的な流れなどを解説します。
目次
1. そもそも療養費とは?
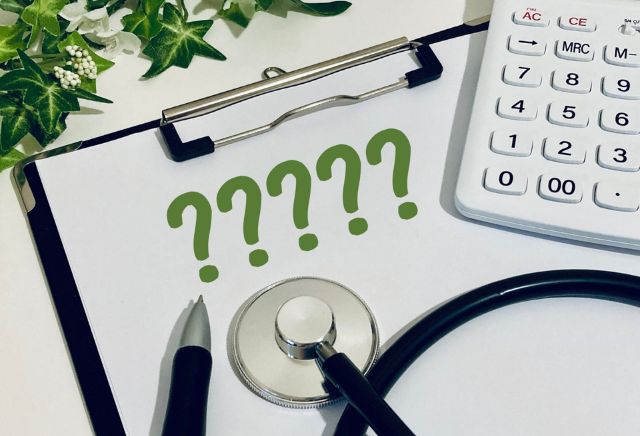
柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師が取り扱える健康保険は、医療機関と大きく異なります。
医療機関では、「療養の給付」といい、保険証を提示すれば医療サービスを受けられる一方で、整骨院での施術は「療養費」という呼び方をします。
療養費は、まずお客様が施術費を整骨院側に全額支払ってから、保険者でより一部負担金額を除き給付を受ける償還払いが基本です。ただし、償還払いの仕組みはお客様にとって使い勝手が良くありません。
そのため、柔道整復師の施術には「受領委任」が認められています。受領委任とは、お客様自身が一部負担金を柔道整復師に支払い、整骨院が被保険者に代わって保険請求を行うという制度です。これにより、整骨院は医療機関と同様に、健康保険証を提示することで最初から一部負担金で施術を受けることが可能です。
ただし、被保険者に代わって保険請求を行うことになるため、療養費支給申請書にサインをしてもらう必要があります。
2. 整骨院で健康保険を取り扱うためには「受領委任契約」が必要!

整骨院で健康保険を取り扱う、つまり保険請求をするためには受領委任契約が不可欠です。
受領委任契約とは、保険請求の仕組みである受領委任制度を利用するにあたって柔道整復師が締結しなければならない契約のことです。柔道整復師が受領委任契約を結ぶことで、お客様から一部負担金を受け取り、保険者に保険請求をする受領委任が行えるようになります。
受領委任契約の方法は大きく分けて「社団法人会員になる」と「個別で受領委任契約を交わす」の2つがあります。保険請求を行いたい柔道整復師の方は以下で紹介する方法を理解して、自分に合った方法を選択すると良いでしょう。
2-1. 受領委任契約の方法(1)社団法人会員になる
受領委任契約を結ぶ1つ目の方法は、社団法人会員になることです。この場合の社団法人とは、「公益社団法人 日本柔道整復師会」や「一般社団法人 日本柔整鍼灸協会」などの柔道整復師にかかわる非営利法人を指します。
柔道整復師が社団法人会員になるときは、下記の流れで手続きをしましょう。
| 1 | 整骨院を開設する |
|---|---|
| 2 | 開設後、10日以内に保健所へ開設届を提出する |
| 3 | 加入する社団法人を選び、入会手続きを行う |
公益社団法人 日本柔道整復師会などの社団法人は、各保険者を管轄する機関との受領委任契約手続きをまとめて行ってくれます。社団法人会員になるだけで保険請求ができるようになるため、受領委任契約にかかわる手続きを省ける点がメリットです。
しかし、加入する社団法人によっては入会金や年会費が必要であったり、独自のルールが設けられていたりするケースがあります。社団法人に加入する場合は、事前に費用や諸条件をよく調べておく必要があるでしょう。
2-2. 受領委任契約の方法(2)個別で受領委任契約を交わす
2つ目の方法が、柔道整復師が個別に地方厚生局などの関係機関と受領委任契約を交わすことです。現在では開業をする多くの柔道整復師が、個別での受領委任契約を選んでいます。
個別で受領委任契約を交わすときは、下記の流れで手続きを進めます。
| 1 | 整骨院を開設し、開設から10日以内に保健所へ開設届を提出する |
|---|---|
| 2 | 地方厚生局や共済組合などに必要書類を提出し、受領委任契約を締結する |
個別で受領委任契約を交わす場合は、地域を管轄する地方厚生局と各機関の規定によって、具体的な手続きや必要書類が異なる点に注意しましょう。
受領委任契約の手続きをスムーズに進めるには、手続きと必要書類を都度確認することが重要です。
3. 【管轄別】個別で受領委任契約を交わす場合の手続きと必要書類

個別で受領委任契約を交わす場合は、保険請求先の保険者を管轄する機関に手続きを行う必要があります。
保険者ごとに受領委任契約を交わす必要がある機関は、下記の通りです。
【社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、船員保険などの保険者】
地方厚生局
【共済組合や自衛隊関係の保険者】
共済組合・防衛省
【労災の指定機関として指定を受ける場合】
労働局
【生活保護の指定機関として指定を受ける場合】
福祉事務所
以下では、それぞれの機関と受領委任契約を交わす場合の手続きと必要書類を説明します。
3-1. 地方厚生局
整骨院で施術を行った後、保険者に保険請求を行うためには、「契約記号番号」が必要です。契約記号番号は、地方厚生局へ届出することで取得できます。契約記号番号は受領委任制度に関係しているため、取得できない場合は保険請求ができなくなる点に注意が必要です。
地方厚生局への届出に必要な書類は、下記の通りとなっています。地域によっては必要書類に違いがある可能性もあるため、事前に管轄の厚生局へ問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
● 確約書(様式第1号)
● 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届け出・申し出(様式第2号)
● 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出(同意書)(様式第2号の2)(施術者以外に柔整整復師がいる場合)
● 誓約書(様式第2号の3)(令和2年6月1日から適用)
● 施術所開設届又は変更届の写し
● 柔道整復師免許証の写し(勤務柔整師を含む)
● 施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
● 実務経験期間証明書の写し
● 施術管理者研修修了証の写し
3-2. 共済組合・防衛省
地方厚生局への届出によって取得できる契約記号番号には、国家公務員関係・自衛隊関係の方が加入する共済組合連盟などは含まれていません。国家公務員関係・自衛隊関係の保険者に保険請求を行うためには、共済組合と防衛省への届出を行い、各番号(共済連盟承諾番号・防衛省番号)を取得する必要があります。
共済組合と防衛相への届出に必要となる書類は、下記の通りです。
【共済組合】
● 柔道整復師免許書(写)(該当する柔道整復師のもの)
● 申請書(様式第1号)
● 確約書(様式第2号)
【防衛相】
● 柔道整復師免許書(写)(該当する柔道整復師のもの)
● 申出書(様式第1号)
● 確約書(様式第2号)
● 通知書(様式第3号)
なお、共済連盟番号は一度取得したら、その後開設場所を変更しても新たに申請をする必要はありません。しかし、変更等の手続きは必要です。その他生活保護・労働災害・通勤災害に関しても、別途手続きが必要です。
3-3. 労働局
整骨院を労災の指定機関として指定を受けたい場合は、各管轄の労働基準局への申請が必要です。労働局への申請に必要となる主な書類は下記の7つですが、「法人経営か」や「柔道整復師が何人在籍しているか」で必要な申請書類が異なることに留意しておきましょう。
● 申出書(様式第1号)
● 確約書
● 「指定・指名機関登録(変更)報告書」
● 保健所開設届(施術所の確認ができるもの)
● 施術所の平面図
● 施術所の周辺図
● 柔道整復師免許書の(写)(該当する柔道整復師のもの)
書類に不備がなければ、約1~3か月後には施術所に通知書が届きます。この通知を受けることで、労災保険の取り扱いが可能となります。
3-4. 生活保護(福祉事務所)
接骨院で生活保護の指定機関として指定を受けるためには、労働局での手続きと同様、管轄の福祉事務所へ申請する必要があります。福祉事務所への申請に必要となる書類は、下記の4つです。
● 指定助産機関・施術機関指定申請書
● 誓約書(指定助産機関・施術機関指定関係)
● 柔道整復師免許書の(写)(該当する柔道整復師のもの)
● 契約書2通(協定を締結している団体に所属していない方)
都道府県によっては上記以外の書類の提出を求められる可能性もあるため、手続き前に問い合わせておくことをおすすめします。
4. 保険請求を始められる時期はいつ?

受領委任契約については、受理された日から有効のため、保険請求は受理された日より取り扱いが可能です。
通常、各所への届出・申請を行うと、後日「承諾通知書」が整骨院宛てに通知されます。この通知書が届いた時点で受領委任契約が正式に結ばれたこととなるため、その日から保険請求を開始できます。
その他の保険取り扱いについては、締日によって開始時期が異なるため、手続きを行う際は提出期限を事前に確認しておきましょう。
なお、保険請求の手続きは「施術所が開設している」という条件でのみ手続きができます。施術所の開設手続きと同時に保険請求を始める場合は、管轄の保健所ならびに厚生局へ問い合わせると良いでしょう。
5. 整骨院における「受領委任契約の方法」と「保険請求の方法」の関係性
柔道整復師が受領委任契約の方法として社団法人会員になる、もしくは個別契約を交わすのどちらを選んだかは、保険請求の請求方法に影響します。
そもそも保険請求の請求方法には、団体請求(請求代行)と個人請求(直接請求)の2つがあります。
まず団体請求とは、柔道整復師が加入した団体が保険請求を代行する方法です。柔道整復師が社団法人会員になった場合は、基本的に加入団体が請求を代行します。
対して個人請求とは、整骨院を経営する柔道整復師自身が直接保険者へと請求する方法です。個別で受領委任契約を交わした場合は個人請求を行います。
団体請求と個人請求のどちらにすべきかで悩んでいる方は、下記の表を参考にメリット・デメリットを比較してみましょう。
| 団体請求 | 個人請求 | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
また、団体請求と個人請求とでは、保険請求から入金までの流れにもいくつかの違いが生じます。
団体請求・個人請求のどちらが良いかを比較検討するときは、保険請求から入金までの流れにおける違いも把握することが大切です。
6. 【3STEP】保険請求から入金までの流れ

保険請求から入金までの流れは、基本的に下記の通りです。
| STEP1 | レセプトを作成し、加入団体もしくは保険者に提出する |
|---|---|
| STEP2 | レセプトの審査が行われる |
| STEP3 | 審査通過後、療養費が入金される |
団体請求と個人請求とで違いが生じるのは、主にSTEP1とSTEP3の部分です。
以下では、保険請求から入金までの流れをより詳しく説明し、団体請求と個人請求における違いも解説します。
6-1. STEP1:受付・レセプト作成
お客様は健康保険を利用して施術を受けた後、1~3割の自己負担分を支払います。残りの9~7割の療養費が、整骨院が保険請求をする金額です。
整骨院が保険請求を行う際は、「レセプト(診療報酬明細書)」を作成します。レセプトとは、お客様の1か月分の診療記録にもとづいて、発生した月間の療養費をまとめた書類です。
作成したレセプトは、団体請求の場合は「加入団体」に提出します。加入団体は受付したレセプトの内容をチェックし、不備がなければ保険者に提出する流れです。
一方で個人請求の場合は、「保険者」にレセプトを直接提出します。
なお、審査支払機関へのレセプト提出期日は、基本的に診療月の翌月10日までです。レセプト提出が遅れた場合はさらに翌月の提出となり、レセプトの審査が遅れて入金も遅くなることに注意してください。
6-2. STEP2:レセプト審査
提出したレセプトは保険者によって審査が行われ、請求が適正であるかを確認されます。
レセプト審査の内容は、主に「内容点検」「受診者照会」の2つです。
| 内容点検 | レセプトに入力ミスや記載の不備がないかを確認する。 |
|---|---|
| 受診者照会 | お客様に対し、レセプトの請求内容と受けた施術の内容が合っているかや、負傷の原因が正確であるかなどを確認する。 |
レセプト審査の結果、不備があった場合はレセプトの返戻(保険者返戻)や減額が行われます。レセプトが返戻された場合は、不備があった部分を修正後にレセプトを再提出しなければなりません。
6-3. STEP3:入金
レセプト審査を通過した場合は、請求した療養費の入金が行われます。
入金時期は請求方法や保険者によって異なり、請求(レセプトの提出)をした月から約2~3か月後とバラつきがあることが特徴です。
一般的に、個人請求のほうが入金スピードは早い傾向があります。団体請求の場合は請求と入金のタイミングで加入団体を通すため、個人請求と比べて+0.5か月程度のタイムラグが発生しやすくなります。
まとめ
近年は最初から個人請求を行い、請求団体には加入しないケースもあります。しかし、個人請求は手続きが複雑なため、いざ施術を開始しようと思った際には、手続きに不備が生じて保険請求ができなくなる可能性もゼロではありません。
この場合、手続きが現状どこまで進んでいるかなどをわざわざ確認する手間も発生します。整骨院開業と保険請求の手続きを同時に進めていた場合は、不備によって開業が遅れるケースも考えられます。
私たち全国統合医療協会は、開業を考えている皆様がスムーズに経営ができるよう無料開業支援のサポートもしております。整骨院開業や保険請求の手続きについてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
また、全国統合医療協会ではその他経営に役立つ豆知識も掲載しておりますので、ぜひあわせてご覧ください。
この記事の監修者

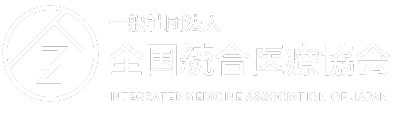




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら