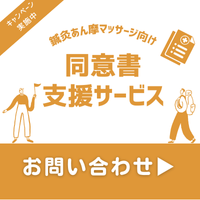訪問マッサージにおける「施術報告書」とは?作成方法・記入例も

整骨院では、通院が困難な患者の自宅や施設に施術者が訪問し、鍼灸・マッサージなどを行う「訪問マッサージ」というサービスを提供できます。この訪問マッサージでは、施術内容を記載した「施術報告書」が、医療関係者との連携や保険請求時の重要な記録として求められます。
当記事では、整骨院が行う訪問マッサージにおける「施術報告書」の概要や作成方法を紹介します。記入例も挙げているため、訪問マッサージの導入を検討している整骨院経営者の方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 【整骨院】訪問マッサージの「施術報告書」とは?

整骨院における訪問マッサージの「施術報告書」とは、 医療機関や医師などへ提出するための、施術内容・経過を記載した書類のことです。
そもそも整骨院の訪問マッサージとは、歩行困難・寝たきりなどで通院が難しい患者の自宅や施設に施術者が訪問し、あん摩マッサージ指圧・鍼灸施術を行うサービスを指します。
訪問マッサージは健康保険が適用されるケースが多く、医師の同意を得たうえで施術を実施します。また、施術を継続する際は医師からの再同意が必要となるため、施術者は一定期間ごとや再同意を求めるタイミングで施術報告書を作成し、医師へ提出しなければなりません。
2. 施術報告書を作成することの重要性

訪問マッサージにおいて施術報告書は義務ではなく、施術者の努力義務とされています。
しかし、施術報告書を作成しなかった場合は医師から施術内容について問い合わせを受け、その都度説明する手間が生じます。双方の作業負担をなくすためにも、基本的には施術報告書を作成しておくのが望ましいでしょう。
また、施術報告書の作成にはその他にもさまざまなメリットをもたらします。ここからは、施術報告書の作成が重要とされる理由について、より詳しく説明します。
2-1. 患者の健康状態を正確に把握できる
施術報告書には、施術時の患者さんの体調や症状のほか、施術内容やそれによる反応などを細かく記載します。これらの情報は、患者さんの健康状態を正確に把握するため、そして経過や変化を継続的に追跡するための重要なデータとして役立ちます。
また、施術報告書は患者さん自身にとっても、施術の履歴や現在の健康状態を客観的に知る手段となります。結果として、施術に対する理解や納得につながるほか、今後の施術計画や療養方針を適切に立てることにもつながります。このように、施術報告書は患者さんと施術者の双方に大きなメリットがあります。
2-2. ほかの医療関係者との連携がスムーズになる
訪問マッサージを利用する患者さんは、並行してほかの医療機関で何らかの治療を受けていることも珍しくありません。こうしたケースにおいて、施術報告書は医療機関間の情報共有を円滑に行うため・円滑な連携をとるための重要な資料となります。
施術報告書を見た医師やケアマネジャーは、患者さんの状態や施術内容を適切に把握でき、医療機関での治療方針や対応にギャップやズレが生じにくくなります。結果として、医療・介護関係者全員で最適なケアを提供できるようになるでしょう。
2-3. 保険請求時の重要な記録になる
施術報告書は、保険請求の際にも重要な役割を果たします。
前述の通り、訪問マッサージは健康保険が適用されるケースが多くあります。整骨院が施術費用を保険者に請求する際は、療養費支給申請書やレセプト(診療報酬明細書)など、「どのような症状に対して、どのような施術を行い、どのような経過があったか」を示した各種書類を整備する必要があります。
施術報告書は保険請求時において、施術の必要性や継続理由を証明する資料として機能します。そのため、施術報告書を作成していない、あるいは内容が不十分のまま提出した場合は、保険者から問い合わせや指摘を受ける可能性が高くなります。最悪の場合保険適用が認められず、患者さん・施術者双方が不利益を被るリスクもゼロではありません。
施術報告書で正確かつ詳細な記録を残しておくことで、保険請求時に必要な情報を速やかに提示でき、スムーズで確実な保険請求を行えるようになります。
2-4. 施術報告書交付料を算定できる
作成した施術報告書を医師へ提出することで「施術報告書交付料」の別途算定が可能となる点も、施術報告書の作成が重要とされる理由の1つです。
施術報告書交付料は健康保険制度にもとづくものであり、作成・提出後の算定が正式に認められています。なお、施術報告書交付料の算定には下記の条件が定められていることもおさえておきましょう。
● 療養費支給申請書に施術報告書の写しを添付する
● すでに施術報告書交付料を算定している場合、その直前に支給を受けた施術の年月をレセプトに記載する
また、同意書や診断書によって施術が認められている期間中に複数回報告書を提出しても、交付料は1回分しか算定できません。こうしたルールを理解したうえで施術報告書を作成・提出することは、適正な保険請求にもつながります。
3. 施術報告書の作成方法
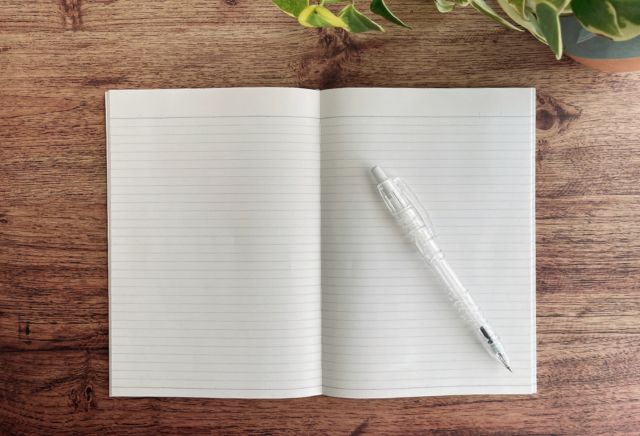
訪問マッサージにおける施術報告書は主に医師へ提出するものであり、下記の項目を記載することが一般的です。
● 患者さんの基本情報(氏名・生年月日・主訴・既往歴など)
● 施術日時
● 施術内容・頻度
● 施術中の経過・症状の変化
● 特記事項
● 今後の施術方針
施術報告書では、これらの基本情報を漏れなく記載しておきましょう。
施術報告書は1から自作しても問題はないものの、できる限り作業効率を高めるためには、必要な項目が整理され、かつ医師が見やすい形でまとめられたテンプレート・フォーマットの活用がおすすめです。施術報告書テンプレートは、厚生労働省や健康保険組合のホームページでも配布されています。
テンプレート選びにおいては、見やすさや実用性だけでなく、内容を容易に更新できるかどうかも重要なポイントです。一人ひとりの患者さんに合わせた施術報告書をスムーズに作成するためにも、パソコンやタブレット上で簡単に編集できるデジタルフォーマットの活用をおすすめします。
4. 施術報告書の記入例
最後に、施術報告書の記入例を紹介します。
実際に記入する際は、各患者さんの状況に応じた具体的な情報を記載し、医師をはじめとした医療関係者が状況を正しく把握できるように意識しましょう。
| 氏名 | 佐藤 花子 |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和20年1月1日 |
| 施術の内容・頻度 | 大腿骨頸部骨折による長期臥床後の下肢筋力低下および関節可動域維持を目的として、下肢中心にマッサージを行っています。特に大腿部・下腿部を中心に軽擦法、揉捏法、圧迫法、関節モビライゼーションを組み合わせ、筋緊張の緩和を図っています。今月は、週1~2回での訪問施術を実施しています。 |
| 状態・経過 | 下肢の筋緊張は緩和傾向にあり、むくみも軽減されています。全体的な筋力低下により、杖歩行でやや不安定な状態が続いていることから、今後も歩行能力維持・生活機能維持を目的とした施術を継続したいと考えています。 |
施術報告書は、専門知識を有した医師が同意・再同意の可否を判断するための資料とは言え、専門用語の羅列はなるべく避け、誰が読んでも分かるような平易な表現を心がけることが大切です。
また、「どの部位に」「どのような目的で」「どのような施術を行っているか」「どのような変化が見られたか」を簡潔かつ具体的に記載することもポイントとなります。
まとめ
訪問マッサージにおける施術報告書は、患者さんの状態管理や医療機関との連携、保険請求において欠かせない書類です。内容や作成方法を正しく理解し、適切に整備することは、円滑な施術継続やトラブルの防止につながります。
全国統合医療協会では、開業・運営支援からレセコン導入支援、医療機器紹介、同意書支援まで、整骨院経営を幅広くサポートしています。訪問マッサージの導入に少しでも不安を抱いている整骨院経営者の方・施術者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

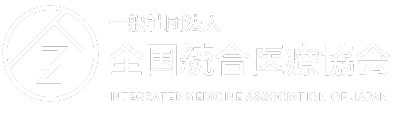




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら