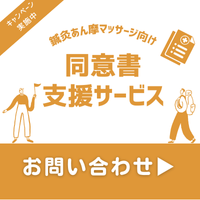【整骨院】後療料の算定に関する基礎知識|算定時のポイントと算定額も

整骨院が算定できる柔道整復療養費の1つに「後療料」があります。整骨院の開業をするにあたって、「後療料とはどのような料金なのか」「何の施術を行えば算定できるか」が気になる柔道整復師の方も多いでしょう。
柔道整復療養費は算定の要件が厳格に定められているため、後療料を算定するにはしっかりとルールを理解することが大切です。
今回は後療料とは何かから、算定条件と算定時のポイント、ケース別での後療料の算定額までを徹底解説します。
目次
1. そもそも「後療料」とは?

後療料とは、柔道整復師が行った「後療(後療法)」という治療に対して発生する料金です。
そもそも「後療」とは、骨折・脱臼・打撲・捻挫といった急性のケガの初期治療を終えたあとに行う、傷付いた組織を回復させるための治療を指します。適切な施術によって部位の機能回復やケガの再発防止を図ることが主な目的です。
整骨院での後療法には、主に下記の3つの手段があります。
| 後療法の手段 | 具体的な施術内容の例 |
|---|---|
| 物理療法 |
|
| 手技療法 |
|
| 運動療法 |
|
なお、骨折・不全骨折または脱臼に関する施術後に、後療として20分程度の運動療法を行う場合は「柔道整復運動後療料」を算定できます。
柔道整復運動後療料の算定額は1日につき320円で、その他の後療料に加算される形です。算定できるのは負傷日から15日間を除いて1週間に1回程度、1か月(歴月)で5回が限度とされています。
2. 整骨院における後療料の算定条件

整骨院が療養費として後療料を請求するためには、後療料の算定条件を満たさなければなりません。条件を満たしていない場合は後療料として算定できないため、整骨院の開業を目指す方は算定条件を正しく理解しましょう。
以下では、整骨院で後療料を算定する際に満たすべき3つの条件を解説します。
2-1. (1)後療として認められる施術である
後療料を算定できるのは、初期治療後に行うリハビリ的な施術(後療)のみです。そのため、初期治療を行う初回の施術では基本的に後療料を算定できず、2回目以降の施術から算定されます。
しかし、他の医療機関または柔道整復師による施術ですでにケガの初期治療を行っているお客さんに対しては、自院で初期治療を行う必要がありません。自院での初回の施術が後療である場合は、初回でも後療料を算定できます。
2-2. (2)施術効果を明確に説明できる施術である
後療料を算定できるのは、行った施術の効果を明確に説明できる場合のみです。たとえば「痛みの緩和のために電気療法を行った」「ケガにより低下した筋力の回復を図るために筋力トレーニングを行った」などのケースであれば後療料を算定できます。
反対に、施術を行った効果・目的を説明できない場合は、後療となる施術を行っても後療料を算定できない点に注意してください。「お客さんに意味もなく温熱療法を行った」では施術効果を説明できず、後療料の算定条件を満たせません。
2-3. (3)医師の同意がある(骨折・不全骨折・脱臼の場合)
骨折・不全骨折・脱臼への後療では、医師の同意が必要です。医師の同意を得た旨は施術録に記載し、柔道整復施術療養費支給申請書の摘要欄にも忘れず記載しましょう。
医師の同意はお客さん自身が得る方法でも、柔道整復師が得る方法でも問題ありません。しかし、医師の同意は書面上ではなく、医師がお客さんを診察した上で同意する必要があります。
また、同意を得る医師の科目は整形外科や外科でなくてもよいとされているものの、医師の科目がケガの治療と関係性が低い場合は認められない可能性があります。療養費請求を円滑に進めるためには、ケガの処置を行った医師から同意を得ることがおすすめです。
3. 整骨院における後療料算定のポイント

整骨院における後療料の算定では、「逓減算定」によって後療料が減額されたり、反対に増額が認められたりするケースもあります。正しい金額で後療料を計算するためには、後療料の算定にかかわるポイントを押さえておきましょう。
ここからは、後療料算定の2つのポイントを解説します。
3-1. 「逓減算定」が適用される
後療料の算定時には、後療を施す部位数や期間・回数によって金額が減額される「逓減算定」というルールが適用されます。
逓減算定が適用される具体的なケガとルール、減額後の金額は下記の通りです。
| 適用されるケガ | 逓減算定の適用条件 | 減額後の金額 |
|---|---|---|
| 骨折・不全骨折 | 部位数が3部位以上 | 所定料金の60%(4部位目以降は3部位目までの料金に含める) |
| 脱臼・打撲・捻挫 | 部位数が3部位以上 | 所定料金の60%(4部位目以降は3部位目までの料金に含める) |
| 後療の期間が5か月超 | 所定料金の75% | |
| 期間が5か月超であり、施術が1か月あたり10回以上 | 所定料金の50% |
3-2. 増額が認められる例外的なケースもある
ケガが骨折・不全骨折の場合、下記の条件をともに満たしていれば、通常よりも高い後療料の算定が認められます。
● 医師によって後療を依頼されている
● ケガによる拘縮が2関節以上に及んでいる
なお、2条件を満たすことによる後療料の増額は、柔道整復運動後療料と同時に加算可能です。
4. 【ケース別】後療料の算定額(2024年6月~)

後療料の算定を行う際は、柔道整復療養費の料金改定によって算定額が変わることにも注意しましょう。2025年5月時点における柔道整復療養費の料金改定は、2024年6月が最新です。
最後に、2024年6月以降の後療料の算定額をケガの施術別に紹介します。
4-1. 骨折
骨折の後療料は「850円」で統一されています。
| 整復料 | 後療料 | |
|---|---|---|
| 鎖骨・肋骨・手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨 | 5,500円 | 850円 |
| 上腕骨・前腕骨・大腿骨・下腿骨 | 11,800円 |
なお、骨折の後療を医師から依頼されていて、かつ拘縮が2関節以上に及ぶ場合は、後療料を1,090円に増額することが認められています。
また、骨折の後療が3部位以上にわたる場合は、3部位目の後療料が60%に減額されます。たとえば骨折が4部位の場合は、下記のように計算します。
● 1部位目と2部位目はそれぞれ850円
● 3部位目は850円×0.6=510円
● 4部位目以降の料金は3部位目までの料金に含める
4-2. 不全骨折
不全骨折では、基本となる後療料は「720円」です。
| 固定料 | 後療料 | |
|---|---|---|
| 手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨 | 3,900円 | 720円 |
| 鎖骨・胸骨・肋骨 | 4,100円 | |
| 上腕骨・前腕骨・下腿骨・膝蓋骨 | 7,300円 | |
| 骨盤・大腿骨 | 9,500円 |
不全骨折の後療を医師から依頼されていて、拘縮が2関節以上に及ぶ場合は、後療料を960円に増額して算定できます。
また不全骨折の後療も、3部位以上にわたる場合は3部位目の後療料が60%に減額されます。たとえば脱臼が3部位の場合は、下記のように計算します。
● 1部位目と2部位目はそれぞれ720円
● 3部位目は720円×0.6=432円
4-3. 脱臼
脱臼の後療では、後療料を「720円」で算定します。
| 整復料 | 後療料 | |
|---|---|---|
| 顎関節 | 2,600円 | 720円 |
| 肘関節・膝関節・手関節・足関節・指(手・足)関節 | 3,900円 | |
| 肩関節 | 8,200円 | |
| 股関節 | 9,300円 |
また、脱臼の後療料は3部位以上で60%、後療期間が5か月超で75%、後療期間が5か月超かつ施術が1か月あたり10回以上で50%になります。
たとえば肩関節の脱臼で後療期間が5か月を超えた場合、後療料は「720円×0.75=540円」です。
4-4. 打撲および捻挫
打撲および捻挫の後療料は「505円」です。
| 施療料 | 後療料 | |
|---|---|---|
| 打撲・捻挫 | 760円 | 505円 |
打撲および捻挫の後療料も、3部位以上で60%、後療期間が5か月超で75%、後療期間が5か月超かつ施術が1か月あたり10回以上で50%の逓減をして算定します。
たとえば背中の打撲で5か月超かつ1か月あたり10回以上の後療を行った場合は、「505円×0.5=253円(小数点以下1桁目を四捨五入で計算)」に減額されます。
まとめ
整骨院が後療料を算定するときは「後療として認められる施術である」「施術効果を明確に説明できる」などの条件を満たす必要があります。逓減算定のルールや増額が認められるケースを把握し、施術ごとの算定額も理解することで、正確な後療料の算定が行えます。
後療料の算定について不安がある方は「全国統合医療協会」にご相談ください。全国統合医療協会では整骨院の開業支援を提供しており、後療料の算定に関する疑問や悩みにお応えします。
この記事の監修者

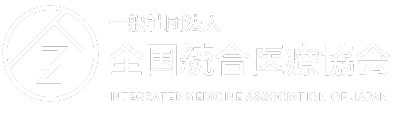




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら