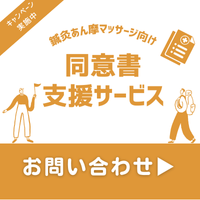整骨院・鍼灸院をフランチャイズ(FC)で開業するためのステップ

整骨院や鍼灸院の開業を目指している方の中には、「個人で一から開業して、本当にやっていけるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際に、集客や経営のノウハウが乏しい状態での開業は、大きなプレッシャーを感じるものです。だからこそ、本部からの継続的なサポートを受けながら自分の店舗を持てる「フランチャイズ(FC)」での開業は、整骨院・鍼灸院の開業に不安を感じる柔道整復師にとって有力な選択肢となるでしょう。
そこで今回は、整骨院・鍼灸院におけるフランチャイズの概要から開業までのステップ、さらにフランチャイズ開業のメリット・デメリットまで分かりやすく説明します。
目次
1. そもそも整骨院・鍼灸院のフランチャイズ(FC)とは?

フランチャイズ(FC)とは、フランチャイズ本部となる親企業と契約を結び、その親企業が有する企業ブランドや運営ノウハウを活用して店舗を展開するビジネスモデルです。
親企業は「フランチャイザー」とも呼ばれ、商品開発や仕入れ先の確保、マニュアル整備、人材育成、広告宣伝などを通してブランド価値の維持やサービスの品質向上に努めます。
一方、加盟店側は「フランチャイジー」と呼ばれ、店舗の売上アップを目指すとともに、ブランドイメージの維持・向上にも貢献します。対価として毎月本部にロイヤリティを支払う義務はあるものの、独自で開業する場合と比べて初期費用を抑えやすい点が大きな魅力です。
なお、フランチャイズ契約を結んでいても、加盟店は独立した事業者として扱われます。そのため、独自で開業するときと同様に「開業届の提出」や「従業員を雇う際の諸手続き」はオーナーの仕事となります。
2. 【5STEP】整骨院・鍼灸院をフランチャイズで開業する流れ

整骨院・鍼灸院をフランチャイズで開業する際の主な流れは、下記の通りです。
| STEP1 | 免許・資格の取得 |
|---|---|
| STEP2 | フランチャイズ本部への問い合わせ |
| STEP3 | 加盟申込・フランチャイズ契約 |
| STEP4 | 物件選定・手続き |
| STEP5 | 開業準備・運営開始 |
ここからは、各ステップの詳細を分かりやすく解説します。
2-1. STEP1:免許・資格の取得
まず前提として、整骨院・鍼灸院を開業するときは国家資格の取得が必要です。
整骨院開業の場合は「柔道整復師」が、鍼灸院開業の場合は「はり師」および「きゅう師」の免許がそれぞれ求められます。いずれも、厚生労働大臣が指定する養成学校や専門学校を修了し、国家試験に合格することで取得できます。
また、保険施術を取り扱う場合は「受領委任」の取り扱いに関する手続きも不可欠です。受領委任の取り扱いを可能とするためには、各店舗に1名以上の「施術管理者」を配置しなければなりません。施術管理者になるための要件としては、1~3年間の実務経験や指定研修の修了が定められています。
このように、フランチャイズ加盟店として整骨院・鍼灸院を開業する場合においても、独自で開業するときと同様に免許・資格や保険関連の諸手続きが必要となります。スムーズな開業を目指すためにも、あらかじめ必要な準備をしっかりと確認しておくことが大切です。
2-2. STEP2:フランチャイズ本部への問い合わせ
開業に先立って必要な免許・資格を取得したら、自分の理想とする経営スタイルや地域での展開に合ったフランチャイズ本部の候補を決定し、電話やメールで問い合わせを行いましょう。
問い合わせを通して、契約条件や提供されるサポートの内容、初期費用、ロイヤリティの仕組みなど、気になる情報を具体的に確認できます。
また、多くのフランチャイズ本部では、開業希望者向けに説明会や個別相談会を実施しており、実際の支援体制や本部の方針についてより深く理解する機会が得られます。開業後の運営に対する不安も軽減され、事業に対する安心感が高まるでしょう。
整骨院・鍼灸院のフランチャイズは、本部によって経営方針やサポートの内容に違いがあります。複数の候補先を比較検討し、理想に合った本部を選ぶことが、長く安定して経営を続けるための重要なカギと言えます。
2-3. STEP3:加盟申込・フランチャイズ契約
フランチャイズ本部の選定が済んだら、加盟申込を行い、具体的な開業準備に進みます。
加盟申込後は、本部との面談や追加の説明会に参加し、本部側による審査を経て、契約条件に双方が合意すれば正式にフランチャイズ契約が締結されます。
この際に交わす契約書には、ロイヤリティの割合や契約期間、ブランド利用の条件、提供されるサポート内容などが明記されています。
開業後のトラブルを避けるためにも、契約書の内容は細部までしっかり確認しましょう。必要に応じて、専門家のアドバイスを受けるのもおすすめです。
2-4. STEP4:物件選定・手続き
開業予定地の物件がまだ決まっていない場合は、契約締結後に物件選定を行うのが一般的です。本部によっては、立地調査や候補物件の紹介、契約手続きのサポートまで行ってくれるケースもあります。
開業場所としては、高齢者が多く住む住宅街をはじめ、昼間人口の多いオフィス街や商店街も有力な候補です。駅やバス停など交通機関からのアクセスが良い場所は通いやすさという点でも利便性が高く、集客にもつながります。
また、自宅の一部を活用して開業したり、内装や設備が整った居抜き物件を活用したりすれば、開業にかかる費用を大きく抑えることも可能です。希望の立地やコストとのバランスを考慮しながら、最適な開業場所を検討しましょう。
2-5. STEP5:開業準備・運営開始
契約締結・物件選定後は、いよいよ開業準備に入ります。
この段階では、フランチャイズ本部から提供されるマニュアルや指導に基づき、内装工事や設備・施術用品の導入を進めます。店舗の立地に合わせた集客戦略や導線設計など、専門的なアドバイスを受けながら準備を整えられる点は、フランチャイズならではの大きなメリットです。
また、スタッフの採用と育成、地域への告知・宣伝活動も重要な準備項目となります。特に開業直後は、地域住民に存在を知ってもらうことが集客の第一歩となるため、ポスティングやSNS活用など、効果的な広告施策を講じることが大切です。
準備が整えば、いよいよ整骨院・鍼灸院として正式にオープンします。開業後も本部からの継続的な経営サポートや研修、マーケティング支援を受けながら、安定した運営を目指しましょう。
3. 整骨院・鍼灸院をフランチャイズで開業するメリットとデメリット

整骨院・鍼灸院をフランチャイズで開業することには一長一短あります。どちらか一方の側面だけで判断するのではなく両方を把握したうえで、自分に合った開業方法を選ぶことが大切です。
最後に、整骨院・鍼灸院をフランチャイズで開業するメリットとデメリットをそれぞれ詳しく説明します。
3-1. メリット
フランチャイズ加盟店として整骨院・鍼灸院を開業するメリットは、下記の通りです。
●本部の屋号を活用できる
すでに市場で広く認知されている本部の屋号を使用できるのは、フランチャイズ開業ならではの強みです。ゼロから知名度や信頼度を築く必要がないため、開業直後でも一定の集客効果が期待できます。
●開業・運営の手厚いサポートを受けられる
フランチャイズでは、本部から整骨院・鍼灸院の運営に関するマニュアルや指導が提供されるため、初めての開業でも安心してスタートできます。集客や経理、スタッフ育成などノンコア業務に関するノウハウも得られる点は、経験の浅いオーナーにとって大きな利点です。
●自宅開業における集客ハードルが低まる
自宅開業は初期費用を抑えられる一方で、集客ハードルの高さが最大の課題となります。しかし、フランチャイズに加盟すれば本部の知名度や集客支援・経営ノウハウを活用しながら自宅開業が可能です。費用を抑えつつ信頼感のあるスタートが切れることから、自宅開業とフランチャイズ契約の相性は非常に良好と言えるでしょう。
3-2. デメリット
フランチャイズ加盟店として整骨院・鍼灸院を開業するデメリットは、下記の通りです。
●ロイヤリティが発生する
フランチャイズで整骨院・鍼灸院を開業した際は、毎月定められたロイヤリティ、または売上に応じたロイヤリティを支払う義務があります。売上が伸びない時期でも一定額の支払い義務がある点や、売上額がアップするほど負担も増加する点は、経営を圧迫させる要因になりかねません。
●経営の自由度が限られる
フランチャイズ本部は、企業ブランドや品質の統一性を保つために厳格なガイドライン・ルールを定めており、加盟店は施術メニューや料金設定、広告宣伝などについて本部の方針に従わなければなりません。独自のアイデアや運営方針を自由に反映させたいと考える開業者にとっては、大きなデメリットとなり得るでしょう。
●契約条件による制約がある
フランチャイズ契約においては、契約期間中の中途解約で違約金が発生するほか、退会後の一定期間は同業種での開業が制限される(競業避止義務)など、基本的に契約上の縛りが生じます。一度加盟するとその後の進路にも何らかの影響を及ぼす可能性があるため、契約内容を慎重に確認しておくことが大切です。
まとめ
整骨院・鍼灸院の開業を検討するうえで、フランチャイズという選択肢は、「ゼロからのスタートに不安がある」「経営や集客に自信がない」と考える方にとって、心強いサポートを得ながら始められる有効な方法です。既存のブランド力や本部の支援を活用することで、スムーズな立ち上げが期待できるでしょう。
ただし、フランチャイズにはロイヤリティや契約上の制約など、独自開業にはないデメリットもいくつか存在します。
どちらの方法が自分に合っているかを見極めるには、客観的な視点からアドバイスを受けることも重要です。「自分に最適な開業スタイルを見つけたい」という方は、ぜひ全国統合医療協会までお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

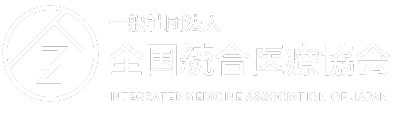




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら