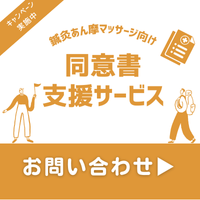整骨院のオペレーションとは?見直しのポイント・代表的な施策も

整骨院の運営・経営を安定化させるためには、施術技術の向上だけでなく、スタッフの動きや院内の流れを含めた仕組みづくりが不可欠です。特に、来院から施術、会計までの一連の流れがスムーズであろうかどうかは、顧客満足度やリピート率に直結します。
来院から会計までの仕組み全体を指す言葉が「オペレーション」です。整骨院におけるオペレーションは、施術の質や接客、院内の環境管理など多岐にわたり、定期的な見直しを行うことでサービスの質や顧客満足度の向上、さらにスタッフの働きやすさにもつながります。
そこで今回は、整骨院におけるオペレーションの概要と基本的な考え方から、見直しのポイント、改善に向けた具体的な施策まで分かりやすく解説します。
目次
1. 整骨院の「オペレーション」とは?

整骨院の「オペレーション」とは、施術に限らず院全体の運営に関わる一連の業務や流れを指します。お客さんが来院してから施術を受け、帰るまでの各プロセス、つまりオペレーションが円滑に進むことで、満足度の向上やリピート率の確保につながります。
具体的には、下記のような業務がオペレーションに含まれます。
| 受付・予約管理 |
|
|---|---|
| 問診・検査 |
|
| 施術 |
|
| 会計・保険請求 |
|
| 院内環境・衛生管理 |
|
| スタッフ管理・教育 |
|
| 集客・マーケティング |
|
このように、整骨院のオペレーションには多岐にわたる業務が含まれ、日々欠かさず行われています。しかしその一方で、日常化しているがゆえに「なんとなく・惰性で」進めてしまっている整骨院も少なくありません。だからこそ、定期的な見直しが必要不可欠です。
2. 整骨院の定期的なオペレーションの見直しが必要な理由

整骨院のオペレーションは、一度仕組み化すれば終わりではなく、定期的な見直しが欠かせません。見直しを怠ると業務が形骸化し、スタッフの作業効率が低下したり、お客さんが求めるサービスと実際の提供内容にズレが生じたりする可能性があります。
ここでは、整骨院のオペレーションの定期的な見直しが必要とされる具体的な理由を紹介します。
2-1. 変化する顧客ニーズへの対応
整骨院を利用する目的は年々多様化しています。かつては外傷や急性痛の緩和といった「対症的な利用」が中心でしたが、近年では再発予防や日常のメンテナンス、さらに疲労回復・リラクゼーション、姿勢・骨盤の美容目的まで裾野が拡大し、中高年だけでなく若年層にも広がっています。
こうした変化に合わせ、整骨院ではメニュー設計や説明トーク、予約導線を定期的に見直す必要があります。予約時間帯の設計、通院頻度の提案、保険・自費の選択肢の提示もアップデートが不可欠です。
2-2. スタッフのモチベーション向上
定期的なオペレーションの見直しは、スタッフの働きやすさにも良い影響をもたらします。
例えばオペレーションの見直しによって、役割分担と標準手順が明確になることで顧客対応の質が安定します。さらに、作業ミスや手戻りによる作業の無駄も削減され、残業の常態化やストレスを抑制することが可能です。
結果として従業員満足度が高まり、多くのスタッフがモチベーションを保ちながら働けるようになるでしょう。
3. 整骨院のオペレーションを見直すときのポイント

整骨院では定期的なオペレーションの見直しが重要であることは理解できても、具体的にどのような観点で見直していけば良いのか分からないという経営者も多くいるでしょう。
整骨院の運営体制の改善には、「QSC」の3つの視点が重要です。Qは施術の質、Sは接客の質、Cは院内環境の清潔さを指します。これらを定期的に確認し、必要に応じて改善しましょう。
3-1. ポイント①Q(クオリティ/施術の質)
Qは、「Quality(クオリティ)」の頭文字をとったもので、いわば施術の品質や技術レベルを指します。痛みや不調の原因を的確に見極め、適切な施術で改善へ導く力は、整骨院にとって欠かせないスキルと言っても過言ではありません。
整骨院全体で施術の質を向上・安定させるためには、定期的な勉強会への参加やスタッフ同士での技術共有が有効です。スタッフ全員が向上心をもち、常に技術のブラッシュアップを意識することで施術品質の向上が見込まれるほか、顧客の信頼獲得にもつながるでしょう。
3-2. ポイント②S(サービス/接客の質)
Sは、「Service(サービス)」の頭文字をとったもので、来院から会計までのすべての接点にあらわれる接客の質を指します。
あいさつや表情、声のトーン、カウンセリングや施術中の声かけなど、細部の配慮が安心感や満足感につながります。画一的な対応ではなく、患者一人ひとりの状態やニーズに寄り添う姿勢は、他院との差別化にもつながるでしょう。
3-3. ポイント③C(クレンリネス/清潔さ)
Cは、「Cleanliness(クレンリネス)」の頭文字をとったもので、院内環境の清潔さを指します。
院内環境の清潔さは、信頼感を左右する重要な要素です。待合室や施術室、トイレの衛生管理のほか、施術ベッド・備品の消毒、整理整頓まで、細部への気配りが求められます。特に、女性や美容目的のお客さんにとって清潔感は「整骨院を選ぶポイント」の1つでもあります。
日頃からすみずみまで清潔にしておくことで、お客さんに「衛生管理が行き届いている」と安心感を与えられるほか、スタッフの作業効率やモチベーションにも良い影響をもたらします。
4. 整骨院のオペレーション改善の進め方|代表的な3つの施策

整骨院のオペレーションを見直すことは、顧客満足度の向上やスタッフの業務効率化に直結します。単に個々の作業を改善するだけでなく、「仕組みそのもの」に注目し、日々の運営フローを整えることが重要です。
最後に、現場で取り入れやすく、かつ施術効果を実感しやすい代表的な3つの施策を紹介します。
4-1. 予約制度の見直し
整骨院においては、受付業務の段階で「電話予約の対応に時間がかかる」「待合室が混雑しやすい」といった課題が生じることもあります。これには、予約管理のデジタル化が進んでいないことや、業務量に対して人員が不足していることが原因として考えられます。
受付業務の課題を解決するためには、オンライン予約システムを導入し、お客さん自身がWebサイトやLINEなどから簡単に予約を取れる仕組みを整えることが有効です。
オンライン予約システムの導入により、受付業務の効率化や予約ミスの防止につながるほか、スタッフの窓口対応負担も軽減されます。また、お客さんの待ち時間も短縮しやすくなり、顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。
4-2. スタッフミーティングの定例化
整骨院では、情報共有が不十分なためにトラブル対応が後手に回るケースがあります。原因としては、院内での口頭やメモによる連絡が中心で、スタッフ間での情報共有の仕組みが整っていないことが考えられます。
課題解決のためには、週1回の短時間ミーティングを定例化し、接客対応や院内運営の情報共有、改善提案を行う場を設けることが効果的です。スタッフ全員が意見を出しやすい環境を作ることで、現場の問題点や改善点を迅速に把握できるようになります。
定例ミーティングの実施により、現場の声が反映されやすくなり、オペレーションの質を継続的に向上させることが可能です。また、スタッフ同士の連携強化によってトラブル対応もスムーズになり、結果的に院全体の運営効率と患者満足度の向上につながります。
4-3. カルテ管理のデジタル化
整骨院では、紙カルテの保管や検索に時間がかかることや、過去の施術情報をスタッフ間で共有しにくいといった課題が生じる場合があります。原因としては、紙媒体のカルテ管理に依存していることや、情報の更新・参照の手間が多いことが挙げられます。
こうした課題に対応するためには、電子カルテを導入し、施術履歴や問診内容をデジタルで一元管理することが有効です。
電子カルテの導入によって、過去の施術内容やお客さんの状態など必要な情報にすぐアクセスできるようになるほか、スタッフ間での情報共有がスムーズになり、施術の質向上や適切なフォローアップが可能となるでしょう。
まとめ
整骨院のオペレーションは、施術の質・接客対応・院内環境の3つの視点「QSC」で定期的に見直すことが重要です。予約制度の整備、スタッフミーティングの定例化、カルテのデジタル化などの具体策を取り入れることで、業務効率が改善し、顧客満足度やスタッフの働きやすさも向上します。
全国統合医療協会では、整骨院の経営に関する幅広いサポートを提供しております。院内運営の仕組みづくりに悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

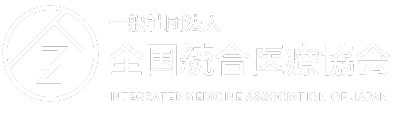




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら