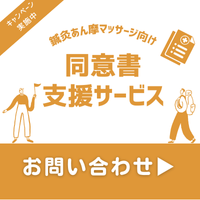鍼灸院におけるカルテの必要性|カルテの種類と選び方も紹介!

病院での治療やレセプト業務などに欠かせないカルテは、鍼灸院や接骨院でも広く活用されています。一般的な病院やクリニックと異なり、鍼灸院にカルテ作成は義務付けられていません。しかし鍼灸院でカルテを活用することで施術の質を高めやすくなり、顧客満足度向上やスタッフの業務効率化に役立ちます。
この記事では鍼灸院におけるカルテの必要性やカルテ導入のメリット、そして鍼灸院におすすめのカルテの選び方について解説します。
目次
1. 鍼灸院における「カルテ」とは?

鍼灸院におけるカルテとは、お客さんの状況を記録し施術方針を決めるためのデータです。鍼灸院で扱うカルテは施術録とも呼ばれ、基本的には初回来院時に記入してもらう問診表とセットになっています。カルテに記入する内容は、おおむね次の通りです。
● お客さんの基本情報(氏名、年齢、性別、住所、連絡先など)
● 初回来院日
● 既往歴、体質(家族歴、服用中の薬、アレルギーの有無など)
● 症状(主訴、その他の気になる症状)
● 施術内容(使用した鍼や灸の種類、ツボの位置、施術時間、補助的な施術について)
● 施術の経過
● 次回以降の施術方針
東洋医学にもとづいてカルテを記入する場合は、これらの内容に加えて脈状や舌診などの情報も記入します。
2. 鍼灸院にカルテが必須となるかは「保険適用の有無」で変わる!
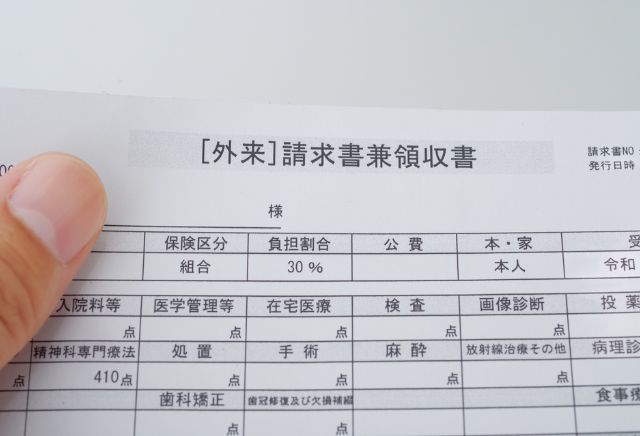
鍼灸院でカルテが必須となるかどうかは、お客さんに提供する施術が自由診療か保険適用かによって異なります。次に、保険適用の有無とカルテの必要性について詳しく解説します。
2-1. 保険適用無し(自由施術)の場合
自由施術とは、公的医療保険が適用されない施術のことで、「自費施術」とも呼ばれます。なお、医療機関においては「自由診療」「自費診療」と呼ばれます。
自由施術は施術料金が全額自己負担となるため、お客さんにとっては負担額が高額になりやすいことがデメリットとなる一方で、施術内容の選択肢が広がりやすいことがメリットです。
自費施術のみの鍼灸院の場合、カルテの作成は義務付けられていません。しかし、詳細なカルテを作成することでさまざまなメリットを得られます。
2-2. 保険適用有り(保険施術)の場合
保険施術とは、公的医療保険を適用できる施術のことで、「保険施術(医療機関においては「保険診療」)」とも呼ばれます。お客さんは、最大3割の自己負担で施術を受けられるようになります。保険を適用することが妥当かどうかを保険組合が判断するためには、詳細に記録されたカルテが欠かせません。
鍼灸院での施術に際して保険を適用するためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
● 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛、頸椎捻挫後遺症などを原因とする慢性症状がある
● 鍼灸院で施術を受けることについて、医師が同意書を作成している(長期間にわたって施術を続ける場合は、6か月ごとに同意書を更新する)
● 対象となる症状について他の医療機関や整骨院などで治療を受けたり、薬やシップを処方されたりしていない
一部の保険組合では、償還払いによって保険が給付されます。償還払いとは、被保険者が一旦全額を自己負担したのちに保険組合へ申請して、保険給付分の払い戻しを受けられる仕組みです。
3. 鍼灸院でカルテを導入するメリット

鍼灸院がカルテを導入することによってより一貫性の高い施術をお客さんに提供しやすくなり、鍼灸院経営のクオリティ向上に貢献できます。
次に、鍼灸院でカルテを導入するメリットについて詳しく解説します。
3-1. お客さんの症状変化を把握しやすくなる
前回の来院時にお客さんが感じていた症状が、今回の来院までにどう変わったかを詳しく記録しておくと、施術前と施術後の症状変化や効果の表れ方を把握しやすくなります。
専門家ならではの視点から客観的なカルテを残すことは、お客さん自身が気づかないような小さな変化を見逃さないためにも重要です。
鍼灸の効果の表れ方は個人差が大きく、同じような症状のお客さんに同じ施術を提供しても効果が表れるタイミングや程度が同じとは限りません。
より多くのお客さんのカルテを残しておくことは、今後新規のお客さんに適切な施術を提供するための手がかりを増やすことにも役立ちます。
3-2. 一人ひとりに合った施術計画を立てやすくなる
カルテに症状の経過や体質を記録しておくことで症状改善までの見通しを立てやすくなり、お客さん一人ひとりに合ったきめ細やかな施術計画を立てる手がかりとなります。
お客さんが鍼の痛みに敏感な場合や施術後思うように症状が改善しない場合なども、カルテの内容に沿って施術方針を柔軟に調整できます。
鍼灸院におけるカルテは、顧客管理やリピーター獲得のツールとしても欠かせません。例えば寒いときに腰痛が出やすいお客さんがいれば、寒くなる時期に合わせて案内用メールやDMを送ることで来院を促しやすくなるでしょう。
3-3. 根拠にもとづく施術の説明がしやすくなる
カルテがあれば、「なぜその施術が必要か」「現在の体の状態がどうなっているか」などの事柄について明確な根拠に沿って説明しやすくなります。お客さんに安心して来院してもらうためには、症状の変化や施術内容について分かりやすく説明し納得してもらうことが大切です。
詳細なカルテを作成することは、一人ひとりのお客さんとしっかり向き合っているという印にもなります。「つらさをわかってくれる」「自分に合った施術をしてくれる」とお客さんに実感してもらうことで信頼関係を築きやすくなり、また万が一のトラブル防止にも役立つでしょう。
3-4. スタッフ同士の情報共有が容易になる
複数のスタッフがいる鍼灸院では、特にカルテの重要性が高くなります。スタッフ同士でカルテを共有しておくことで、担当スタッフの不在時に来院したお客さんに対しても別のスタッフが質の高い施術を提供しやすくなるでしょう。
院内スタッフ以外の相手との情報共有にも、カルテが役立ちます。例えば引っ越しなどの理由でお客さんが他の鍼灸院などへ通うことになった場合、カルテを作っておくことで転院に必要な引き継ぎを進めやすくなります。
交通事故治療に対応している院の場合、保険組合はもちろんお客さんのかかりつけ医師や弁護士などとの情報交換にもカルテが欠かせません。
4. 鍼灸院のカルテの種類

鍼灸院のカルテは紙カルテと電子カルテの2種類に大きく分かれており、いずれも鍼灸院に特化したテンプレートが広く活用されています。
次に、紙カルテと電子カルテそれぞれの特徴について詳しく解説します。
4-1. 紙カルテ
昔から使用されている紙カルテはパソコンに不慣れなスタッフでも扱いやすく、お客さんの動きに合わせてカルテを回すことで順序よく記入できます。また、電源がいらないためカルテ自体が破損しない限り停電時や災害時なども利用可能です。導入・維持コストが安い紙カルテは、開業したばかりの小規模な院にもおすすめです。
近年は多くの鍼灸院や医療機関でカルテの電子化が進んでいますが、紙カルテならではのメリットもあります。カルテの運用方法やスタッフの意見によっては、紙カルテと電子カルテを併用することも一つの方法です。
4-2. 電子カルテ
電子カルテを導入することで必要な情報を素早く検索でき、書き間違いや読み間違いによるヒューマンエラー防止に役立ちます。加えて、広い保管スペースがいらないことや複数のスタッフが同時に閲覧できることも電子カルテの特徴です。パソコンやスマホの操作に慣れたお客さんが多い場合は、カルテとともに問診票を電子化して問診票記入の手間を省くこともよい方法です。
電子カルテは、オンプレミス型(自社運用型)とクラウド型の2種類に分かれます。それぞれの概要と主なメリットは、次の通りです。
| 【オンプレミス型電子カルテ】 | |
|---|---|
| 概要 | 院内にサーバーと専用機器・端末を設置し、自院のネットワーク上でデータを保存・管理するタイプの電子カルテです。 |
| 主なメリット |
|
| 【クラウド型電子カルテ】 | |
|---|---|
| 概要 | インターネット回線を利用して、外部のクラウドサーバー上でデータを保存・管理するタイプの電子カルテです。 |
| 主なメリット |
|
オンプレミス型とクラウド型には、それぞれ異なるメリットがあります。電子カルテを導入する際は、自院の規模や運用方法に合ったものをじっくり比較検討するとよいでしょう。
まとめ
鍼灸院においては、保険施術の場合を除いてカルテ作成は必須ではありません。しかしカルテを通じてお客さん一人ひとりの情報を的確に把握することでオーダーメイドの施術計画を立てやすくなり、顧客満足度向上に役立ちます。
全国統合医療協会では、電子カルテとともにレセプト作成や受付・会計業務なども一元管理できるレセコンシステム「メディネス」を提供しています。これから鍼灸院を開院したい方はもちろん、さらなる顧客満足度向上やスタッフの業務改善を図りたい方も、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

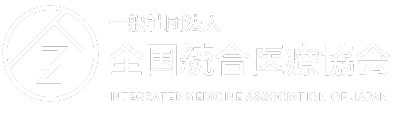




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら