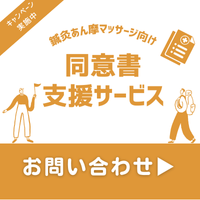【整骨院】レセプトの転帰とは?重要性・注意点・効率化のカギも

整骨院をはじめとする施術所では、日々の施術内容を記録し、保険請求を行うために「レセプト(療養費支給申請書)」を作成します。このレセプトには、お客さんごとの施術日数や部位、負傷名といった基本情報に加えて、「転帰」という項目も設けられています。
レセプトの転帰を適切に記載することは、保険請求の正当性を担保するうえで欠かせません。曖昧な判断や誤った分類をしてしまうと、査定リスクが高まったり、施術所としての信頼性を損ねる可能性もあります。
そこで今回は、「転帰」の基本的な種類や判断基準を解説するとともに、分類作業で注意すべきポイントや、業務効率化につながるヒントも紹介します。整骨院運営に関わる方は、ぜひ日々のレセプト業務にお役立てください。
目次
1. レセプトの「転帰」とは?4つの種類とその判断基準

整骨院で施術を行った際には、施術内容にもとづいて「療養費支給申請書」とも呼ばれるレセプトを作成し、審査支払機関などに提出します。このレセプトには、負傷部位や施術日数などの基本情報に加えて、「転帰」という項目があります。
転帰とは、施術の状況(経過・結果)を示すもので、いわば「今回の施術によってその経過や見通しがどのような形で区切りを迎えたのか」を記録するものです。
保険請求の適正性を判断する材料となる重要な情報であり、記載内容によっては審査や査定に影響を及ぼす可能性もあるため、適切な理解と運用が求められます。
また、転帰には大きく分けて「治癒」「中止」「転医」「継続」の4つの種類があります。まずは、各種類の意味や使い分けの基準について詳しく紹介します。
1-1. (1)治癒
「治癒」とは、負傷部位の症状がある程度おさまり、次の施術は必要ないと判断できる状態になった場合に使用できる区分です。整骨院での施術時に症状が消失している場合は、前回の施術日が治癒日となります。
ただし、「来院しなくなった=治癒」とみなすのは適切ではなく、あくまで施術者が症状の消失や機能の正常化を確認したうえで判断する必要があります。お客さん本人の申し出や主観だけで治癒とするのではなく、施術記録や所見に基づいた判断が重要です。
1-2. (2)中止
「中止」は、お客さんの都合や希望で施術を途中で終える場合に使用する区分です。例えば、通院が困難になった、転居した、またはお客さんが亡くなってしまったといった理由で施術を行えなくなったケースは、中止に該当します。
また、中止の場合は、「症状の回復が不十分なまま通院が終了している」という点に注意が必要です。たとえ「治癒したのではないか」と予測できる状況にあっても、実際にお客さんが来院しておらず施術の継続が確認できない以上、施術者の判断だけで中止とすることはできません。
中止はあくまでも、「やむを得ない理由で通院が途絶えた」という事実に基づいて記載されるべき転帰であり、実際の状況に即して分類することが求められます。なお、中止に分類する際は、通院終了の理由を記録に残しておくことが大切です。
1-3. (3)転医
「転医」は、お客さんがほかの施術所や医療機関に移った場合に使用する区分です。例えば、「整形外科で精密検査を受けたい」「別の整骨院に通うことにした」といった場合が該当します。
転医を記載する際、次に通う予定の施設名までは記載不要ですが、「お客さんが転医の意志を示したこと」「施術を継続するための紹介を行ったこと」などを記録に残しておくことが重要です。単なる通院中断としっかり区別するためにも、施術者が転医の意思を把握した明確な根拠を記載しておきましょう。
1-4. (4)継続
「継続」は、負傷の回復にはまだ時間がかかり、引き続き施術が必要だと判断した場合に使用する区分です。
なお、レセプトでは明確な施術の終了(治癒・中止・転医)がない場合、レセプトの転帰欄は記載せずに提出するのが一般的です。つまり「継続」は、あえて記載しないことで示される区分であり、ほかの区分とは違ってレセプト上では基本的に無表示となります。
しかし、継続が長期にわたる場合には、保険者から「なぜ長期施術が必要なのか」という点を問われることもあります。そのため、毎月のレセプト提出時には症状の改善状況や施術の継続理由を明確にしておくことも大切です。
2. レセプトの転帰を適切に分類することの重要性

整骨院におけるレセプト業務では、転帰の区分を正しく分類することが重要です。転帰欄で施術の経過や通院の状況を適切に示しておかなければ、さまざまなリスクにつながる可能性があります。
ここでは、レセプトの転帰を適切に分類することの重要性を解説します。
2-1. 保険請求の適正性を示せる
療養費の保険請求では、「いつからいつまで施術を行ったのか」「その施術はどのような経過をたどったのか」といった情報を明確に示す必要があります。転帰の記載はその根幹に関わるものであり、適切に分類されていない場合、レセプトの返戻(保険者による差し戻し)リスクが高まります。
特に注意したいのが、長期間にわたって「継続」が続いているケースです。施術が数か月以上に及びながらも継続理由が示されていなければ、保険者側から疑義照会を受けたり、監査の対象になったりする可能性があります。
このように、「いつまでも施術継続」「治癒していないのに治癒扱い」といった不適切な転帰の分類は、不正請求とみなされるおそれもあるため注意が必要です。
こうしたリスクを避けるためにも、施術の経過やお客さんの来院状況に応じて、正しい転帰を判断・記載することが大切です。適切な分類は、保険請求の正当性を裏づけるものであり、結果として自院の信頼性や安全性を守るリスクマネジメントにもつながります。
2-2. 経営分析・改善につながる
転帰の分類は、単なる保険請求のためだけでなく、整骨院の経営分析にも役立ちます。
例えば「中止」が多く見られる場合は、お客さんが施術の途中で離脱していることを意味し、通院継続率に課題がある可能性があります。「転医」が多い場合は、特定の症例において他院への紹介や連携体制を見直すきっかけになるでしょう。また、「治癒」の割合が高ければ、施術効果や顧客満足度の指標として活用できます。
このように、数字の裏にあるお客さんの行動や施術効果を読み解くことで、あらゆる改善点が見えてきます。
加えて、転帰を明確にしておくことは、次回来院がないお客さんへのフォローアップを検討する際の判断材料になります。カルテの整理や施術記録の棚卸しにもつながるため、業務効率化の観点からも意義のある取り組みと言えるでしょう。
3. レセプトの転帰の分類作業で注意すべきポイント

レセプトの転帰の分類作業には、間違えやすい点がいくつか存在します。特に、「治癒」「継続」と「中止」の使い分けや、区分による月内の施術部位数への影響はより気を付けなければなりません。
ここでは、転帰の分類作業でおさえておきたい2つの注意点を詳しく紹介します。
3-1. 「治癒」「継続」と「中止」の使い分け
レセプトの転帰で最も混同されやすいのが、「治癒」と「中止」、そして「継続」と「中止」の区別です。
例えば、「症状は少し残っているものの、施術を続けるほどではなくなった」というケースでは「中止」を使用する方も多くいます。しかし、その後もお客さんが継続して来院している場合は、症状の緩和が確認・推測できることから「治癒」に分類すべきです。
さらに、「お客さんが入院などで通院できなくなった」というケースでは「中止」にあたりますが、退院後に来院が再開された場合は「継続」となります。この場合、摘要欄には「前回は「中止」としたが〇月〇日に来院があり、「継続」に変更した」という旨を明確に記載することが重要です。
3-2. 転帰の違いによる月内の施術部位数への影響
レセプトの転帰の分類は、同じ月内の施術部位数に直接影響します。具体的には、その月に「中止」とした部位は施術部位数として残り、後療料の逓減対象となるため、請求金額に影響が出やすくなります。
例えば、同月内で2部位を「中止」とし、その後別の2部位を新たに施術した場合、月内の最終的な施術部位数は4部位のまま変わらず、後療料の逓減が発生することがあります。
一方で、同じく2部位を「治癒」とした場合は、その分の施術部位数が減少します。よって、同月内に新たに施術した2部位と合わせて施術部位数は2部位となり、後療料の逓減がかからず全額算定が可能です。
このように、転帰の違いによる月内の施術部位数への影響を正しく理解し適切に分類することは、請求の正確性を保つだけでなく、返戻リスクの軽減にもつながります。
4. レセプトの転帰の分類作業を効率化するためには?

転帰の分類をスムーズに行うには、レセプトの電子化、つまりレセコンの活用が大きなカギとなります。
手書きでは毎回記入が必要だった転帰項目も、レセコンならプルダウンやチェックボックスで選択できるため、記載ミスを減らしながら作業効率を高められます。
また、一定期間通院がないお客さんを自動的に「中止」と判定するなど、ルールに基づいた自動処理機能を備えたレセコンもあり、判断の手間も軽減されます。
さらに、転帰に関する情報を自動で集計・分析できる機能があれば、経営面での活用も可能です。効率化と同時に返戻リスクを減らすためにも、レセコンの積極的な導入を検討しましょう。
まとめ
レセプトの転帰とは、施術の状況(経過・結果)を示す項目です。整骨院のレセプトにおける適切な転帰の分類は、返戻防止や適正請求のために重要となります。特に「治癒」「中止」「継続」の正しい使い分けや、施術部位数への影響には注意しておきましょう。
レセプトの転帰の分類作業を効率化するためには、レセコンの導入・活用がおすすめです。全国統合医療協会では、鍼灸整骨院のレセコンシステム「メディネス」を提供しております。転帰の分類作業に限らず、日々のレセプト業務を効率化したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

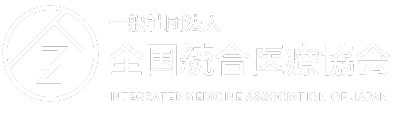




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら