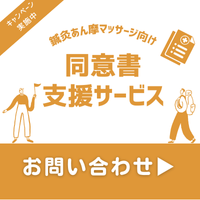【整骨院】自費施術の料金設定|保険施術との違い・ポイント・注意点

整骨院の経営において、自費施術の導入や料金設定は収益向上のカギを握る重要な要素です。しかし、保険施術とは異なり、価格や提供内容を自由に決められる一方で、お客さんに納得してもらえるだけの根拠や工夫も求められます。
保険施術との違いを明確にしないまま、費用対効果ばかりを重視して自費メニューを追加すると、リピート率の低下や信頼の損失につながるおそれもあります。
そこで今回は、整骨院における保険施術と自費施術の違いを整理したうえで、自費施術の料金設定に関するポイントや注意点について詳しく解説します。自費施術の料金設定に悩んでいる整骨院経営者は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. そもそも「保険施術」と「自費施術」の違いは?

整骨院では、施術内容に応じて「保険施術」と「自費施術」の2つの区分が存在します。この2つは対象となる症状や料金の取り扱いが大きく異なり、施術の説明や料金提示を行う際に明確に区別する必要があります。
そこでまずは、保険施術と自費診療の特徴と違いを紹介します。
1-1. 保険施術
保険施術とは、骨折や脱臼をはじめとした急性の外傷性のけがに対し、健康保険を適用して行う施術です。整骨院で保険施術の対象となるのは、あくまで負傷原因が明確な外傷に限られ、肩こりや慢性腰痛といった慢性的な症状は基本的に保険が適用されません。
| 保険施術の対象となる症状 |
|
|---|
施術費用は、厚生労働省が定める「療養費の算定基準」に基づいて全国共通の料金が設定されており、整骨院ごとに自由に料金を増減させることは認められていません。お客さんはこのうち1~3割の「一部負担金」を窓口で支払い、残りは保険者(健康保険組合など)に請求される形で処理されます。
整骨院の経営者にとっては、保険施術の範囲や料金体系を正しく理解し、制度に則った適正な請求を行うことが重要です。違反した場合、保険請求の返戻や指導、場合によっては監査や処分の対象となる可能性もあるため、特に注意が必要です。
1-2. 自費施術
自費施術とは、健康保険が適用されず、お客さんが全額自己負担で受ける施術を指します。代表的な自費施術の例としては、肩こりや慢性的な腰痛に対する施術のほか、姿勢矯正、骨盤矯正、美容整体、リラクゼーションマッサージなどが挙げられます。近年では、ニーズの多様化を背景に、多くの整骨院が自費メニューを導入しています。
自費施術の大きな特徴は、施術内容や料金を整骨院側が自由に設定できる点です。保険施術のような国が定めた基準はないため、各整骨院の方針やターゲットに合わせた価格戦略を立てることが可能です。一方で、施術内容や効果、料金の妥当性をお客さんに納得してもらうための説明責任がより重要となります。
また、保険施術・自費施術を問わず領収書の発行が義務付けられており、発行拒否や不当な内容の記載は認められていません。料金設定とともに、法的な対応も正しく行うことで、信頼される整骨院づくりにつながります。
2. 自費施術における料金設定のポイント

自費施術の料金設定は、整骨院経営において自由度が高い反面、慎重な判断が求められます。適切な料金設定に向けては、「相場の把握」「ターゲット層との整合性」「施術内容の付加価値」など、いくつかのポイントを踏まえておくことが重要です。
●相場を把握する
料金設定の出発点として、まずは自費メニューごとの相場を把握しておくことが大切です。施術1回あたりの一般的な相場は、骨盤矯正で約2,000~5,000円、カイロプラクティック(部位ごと)で約2,000~3,000円、EMSで約3,000円程度となります。これらの相場を基準に、地域性や提供する内容に合わせた柔軟な価格設定を検討していきましょう。
●ターゲット層に合わせた価格設計をする
相場を踏まえつつ、実際に来院が見込まれるターゲット層との相性を考えることも重要です。例えば、主婦層が多い地域では手ごろな価格帯が求められることが多く、反対にビジネスマンや美容目的の女性が中心のエリアでは、高単価でも専門性や快適さが重視される傾向にあります。
●施術の付加価値を明確にする
自費施術では、「時間の長さ」「施術者の技術レベル」「使用する医療機器」など、保険施術ではカバーできない価値を提供できる点が強みです。これらの付加価値を料金に反映させることで、お客さんにも納得感を与えやすくなります。例えば、EMS機器を使用した施術や専門性の高い手技療法などは、その価値を明確に説明した上で、相応の価格設定が可能です。
●保険施術とのバランスを意識する
自費メニューは、保険施術との整合性をとることも重要です。特に、「保険の範囲では対応できない慢性的な不調のケア」や「再発予防のメンテナンス」などを目的とした自費施術なら、お客さんにも違和感なく受け入れてもらいやすくなります。ただし、保険施術と自費施術を同一の治療部位・同一時間帯で併用することは「混合診療」にあたるおそれがあるため、線引きは明確にしておく必要があります。
3. 自費施術の料金を設定する際におさえておくべき注意点

整骨院や接骨院が自費施術を導入する背景には、「保険施術だけでは収益確保が難しい」「幅広いニーズに応えたい」といった理由があります。
しかし、自費施術は自由度が高い反面、料金に関するトラブルやクレーム、経営バランスの乱れといったさまざまなリスクも伴う点に注意が必要です。リスクを防止するためにも、ここから紹介する3つのポイントを意識して料金を設定しましょう。
3-1. 保険施術と自費施術の違いを明確にする
自費施術を導入する際は、まず保険施術との違いをお客さんにしっかりと伝えることが重要です。保険施術との違いをお客さんにも理解してもらっていなければ、混乱を招き、トラブルが発生する可能性もあります。
特に料金については、保険施術と自費施術の料金表を分けて作成し、分かりやすい場所に掲示するのがポイントです。
保険施術は国の定める基準に基づく一律料金ですが、自費施術は内容に応じて自由に金額を設定できるため、その違いを視覚的に伝えることで、お客さんの誤解を防ぐことができます。
3-2. 自費施術の料金を安易に変更しない
「思ったより集客できなかった」といった理由で、頻繁に料金を変更するのは避けるべきです。施術料金の変更は、お客さんに対して「この整骨院は方針が安定していない」「値付けに一貫性がない」といった不信感を与えることになりかねません。
また、変更のたびに既存のお客さんへの説明が必要となり、スタッフの対応負担が増す可能性もあります。価格の見直しを行う場合は、ある程度の期間を設けて検討し、その背景や意図を丁寧に説明することが信頼維持につながります。
加えて、自費施術を新たに導入したからといって、その自費施術ばかりを強調し始めるのも避けましょう。既存の保険施術のお客さんが置き去りにされたと感じないよう、バランスのとれたサービス提供を意識することが大切です。
3-3. 「投資の回収」ばかりに目を向けない
自費施術を始めるにあたっては、高機能の施術機器や専用ベッドの導入など、大きな初期投資が必要になるケースもあります。そのため、「投資をできるだけ早く回収したい」と考える経営者も少なくありません。しかし、その意識が先行して高額な料金を設定することは、かえってリスクになります。
施術内容に対して価格が高すぎると、お客さんは「費用に見合った価値があるのか」と不信感を抱き、リピートにつながりにくくなります。
基本的に投資の回収には一定の時間がかかるものであると理解し、「どのくらいの期間でどの程度の収益が見込めるのか」といった収支計画をあらかじめ立てておくことが大切です。そのうえで、地域の相場やお客さんの経済的負担を考慮し、無理のない料金設定を心がけましょう。
まとめ
整骨院で行われる施術には、保険適用の「保険施術」と、自由診療の「自費施術」があります。自由度の高い自費施術の料金設定においては、お客さんとの信頼関係と経営安定の両立を意識した丁寧な設計が不可欠です。短期的な利益ではなく、長期的な視点で判断することが、安定した整骨院運営につながるでしょう。
全国統合医療協会では、整骨院の運営や制度対応、メニュー設計など、経営に関する幅広いサポートを提供しております。自費施術の導入や料金設定についてお悩みの方は、全国統合医療協会までお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

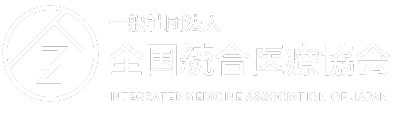




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら