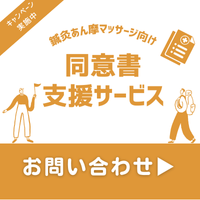【整骨院】柔道整復の「近接部位」とは|算定方法と算定時の注意点も

整骨院をスムーズに経営するためには、保険請求を適正に行うことが大切です。しかし、柔道整復における療養費の算定では「近接部位」のような複雑に感じられるルールもあり、適切な保険請求ができるか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、柔道整復における「近接部位」の定義や考え方、近接部位の具体例について解説します。近接部位の算定方法や特殊な近接部位、算定時の注意点も併せて確認し、適正な保険請求と円滑な整骨院経営を目指しましょう。
目次
1. 柔道整復における「近接部位」とは?

近接部位とは、その言葉の通り、解剖学的に非常に近接している体の部位のことを指します。
整骨院では、施術部位ごとに療養費を算定するのが一般的です。しかし、2つ以上の極めて近い部位(近接部位)を同時に施術する場合、一方の施術でもう一方の部位の施術も行ったとみなされます。したがって、近接部位である2つの部位を施術する際には、一方の療養費は算定できるものの、もう一方の部位の療養費を算定することはできません。
このように、整骨院の柔道整復において、両方の部位の療養費を同時に算定できない近接する部位どうしを「近接部位」と呼びます。
近接部位の施術で両方の部位の療養費を算定した場合、不正請求と判断され、返戻請求や行政処分といったトラブルに発展する恐れがあることに注意が必要です。近接部位では一方の部位しか療養費を算定できないというルールを理解するとともに、近接部位にはどのような部位があるか、十分に把握しておきましょう。
2. 整骨院で療養費の算定(請求)ができない近接部位の例

近接部位の定義や算定例については、厚生労働省が発行する「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」に明記されています。ここでは、療養費を同時に算定することができない近接部位の負傷例について、詳しく確認しましょう。
出典:厚生労働省「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の実施上の留意事項について」(スライド9)
2-1. 骨折・不全骨折
骨折や不全骨折は整骨院でよく見られる負傷の1つであり、近接する部位も同時に何らかの負傷があるケースも少なくありません。骨折・不全骨折が見られる部位の算定と同時に算定を行えない近接部位の負傷例としては、下記のようなものが挙げられます。
| 種類 | 算定できない近接部位の負傷例 |
|---|---|
| 鎖骨骨折 |
|
| 上腕骨骨折(下部) |
|
| 下腿骨骨折(上部) |
|
上記の負傷および近接部位は、あくまで一例です。肋骨骨折や手根骨骨折、趾骨骨折などさまざまな種類で算定できない近接部位があるため、厚生労働省の資料を十分確認しておきましょう。
出典:厚生労働省「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の実施上の留意事項について」(スライド9)
2-2. 脱臼・打撲・捻挫・挫傷
脱臼や打撲、捻挫、挫傷といった負傷においても、療養費を同時に算定できない近接部位があることに注意が必要です。厚生労働省が明示している具体的な例をいくつか確認してみましょう。
| 種類 | 算定できない近接部位の負傷例 |
|---|---|
| 頸部捻挫 |
|
| 背部打撲(または挫傷) |
|
| 足関節脱臼・捻挫 |
|
脱臼や打撲、捻挫、挫傷における近接部位は、上記以外に複数存在しています。複数部位の負傷について施術する場合は、近接部位の関係にあるかどうかを事前に確認した上で、保険請求時のミスがないようにしておきましょう。
出典:厚生労働省「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の実施上の留意事項について」(スライド9)
3. 近接部位の算定方法

近接部位を施術する場合、どちらか一方の療養費しか算定できません。厚生労働省は算定の方法についても定めているため、ルールに則り施術料を算定することを心がけましょう。
【近接部位の算定方法】
| 負傷の種類 | 同時に発生した近接部位の負傷の種類 | 算定方法 |
|---|---|---|
下記のいずれか2つの部位の捻挫
|
|
捻挫に対する所定料金のみにより算定する |
| 左右の肩関節捻挫 |
|
左右の肩関節捻挫に対する所定料金のみにより算定する |
| 顎関節の捻挫 | 同側の顔面部打撲 | 捻挫に対する所定料金のみにより算定する(※) |
| 指・趾骨の骨折または脱臼 | 指・趾骨の不全骨折・捻挫または打撲 | 骨折または脱臼に対する所定料金のみにより算定する |
| 関節近接部位の骨折 | 当該骨折の部位に最も近い関節の捻挫 | 骨折に対する所定料金のみにより算定する |
(※)顎関節の捻挫は左側と右側のそれぞれを1部位として捻挫の所定料金を算定可能
なお、関節捻挫と同時に発生した関節近接部位の打撲または挫傷については、捻挫に対する所定料金のみにより算定します。このケースでは、次の場合を除外して当該捻挫の部位から上下2関節までを範囲とすることを押さえておきましょう。
● 手関節捻挫・前腕部打撲または挫傷(上部のみ)
● 肘関節捻挫・前腕部打撲または挫傷(下部のみ)
● 肘関節捻挫・上腕部打撲または挫傷(上部のみ)
● 肩関節捻挫・上腕部打撲または挫傷(下部のみ)
● 足関節捻挫・下腿部打撲または挫傷(上部のみ)
● 膝関節捻挫・下腿部打撲または挫傷(下部のみ)
● 膝関節捻挫・大腿部打撲または挫傷(上部のみ)
● 股関節捻挫・大腿部打撲または挫傷(下部のみ)
出典:厚生労働省「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の実施上の留意事項について」スライド8「(1) 近接部位の算定方法」
4. 特殊な近接部位について
近接部位を理解するだけでも大変ですが、さらに特殊な近接部位があることにも注意が必要です。代表的な特殊近接部位として2つのパターンがあるため、それぞれについて確認しておきましょう。
1つ目のパターンとして、頸部、両肩、腰部のいずれか2つの部位の捻挫と、背部の打撲(または挫傷)の組み合わせが挙げられます。例えば、左肩関節捻挫と頸部捻挫、背部打撲を同時に扱う場合は、特殊近接に該当して各部位の施術を同時に算定することはできません。
2つ目のパターンとして、頸部と両肩の捻挫の組み合わせがあります。頸部捻挫と左肩関節捻挫、右肩関節捻挫を併発している場合は、特殊近接として保険請求を行う必要があることを押さえておきましょう。
なお、この2つのパターンの特殊近接は3つの部位の組み合わせであることから、「3部位セットの近接」と呼ばれることもあります。
この2つの特殊な近接部位は3部位の組み合わせの近接であることから、「3部位セットの近接」と呼ばれることもあります。各部位の負傷日が異なる場合でも、同時に施術を行えば近接に該当することにも留意しましょう。
5. 整骨院で近接部位を算定するときの注意点

整骨院で近接部位を算定する際には、保険請求をスムーズに進めるために注意すべきポイントがいくつか存在します。
ここでは、近接部位を適正に算定するために気を付けたい3つの注意点について詳しく確認しておきましょう。
5-1. 協定傷病名を使用し上下左右をつける
協定傷病名を使用する場合、近接部位であるかどうか関係なく、必ず上下左右をつけることを心がけましょう。近接部位である場合のみに上下左右をつけ、それ以外の場合にはつけていない場合、その部位に対して意図的に部位操作をしていると保険者から疑われる恐れがあるためです。
また、上下左右をつけずに請求した場合、翌月に関して近接を避けられない可能性もあります。近接部位かどうかにかかわらず、上下左右をつけて保険請求トラブルを回避しましょう。
5-2. 協定外傷病名は使用しない
近接部位を記載する場合、協定外傷病名(協定傷病名以外の傷病名)は使用しないようにしましょう。
協定傷病名は近接かどうかを判断するルールがありますが、協定外傷病名にはそのような規定はありません。また、協定傷病名と協定外傷病名が近接かどうかを判断するルールも定められていないため、保険者の判断で返戻される恐れがあることに注意が必要です。
5-3. 肩甲部打撲は使用しない
傷病名として「肩甲部打撲」を使用することも避けたほうがよいでしょう。
肩甲部打撲は、基本的には背部打撲として取り扱うことが定められており、「肩甲部打撲」を使用すると「肩関節+背部挫傷(上部)」という扱いになってしまいます。近接の範囲が広くなり、同時に算定できなくなる部位が増える恐れがあることに注意してください。
まとめ
柔道整復における「近接部位」は、解剖学的に非常に近接している部位であり、同時に施術した場合に一方の療養費しか算定できない部位の組み合わせのことを指します。近接部位の例や算定方法については厚生労働省がルールを定めているため、資料を十分にチェックしておきましょう。特殊な「3部位セットの近接」にも注意が必要です。
整骨院で近接部位を算定する際に注意すべきポイントはいくつかありますが、これらに気を付けていても保険請求に不安を感じる方もいるでしょう。算定や保険請求に不安がある方は、整骨院経営に関する豊富な知識・ノウハウを有する「全国統合医療協会」にぜひご相談ください。
この記事の監修者

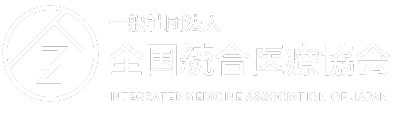




 サービス資料
サービス資料 レセコン
レセコン お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら